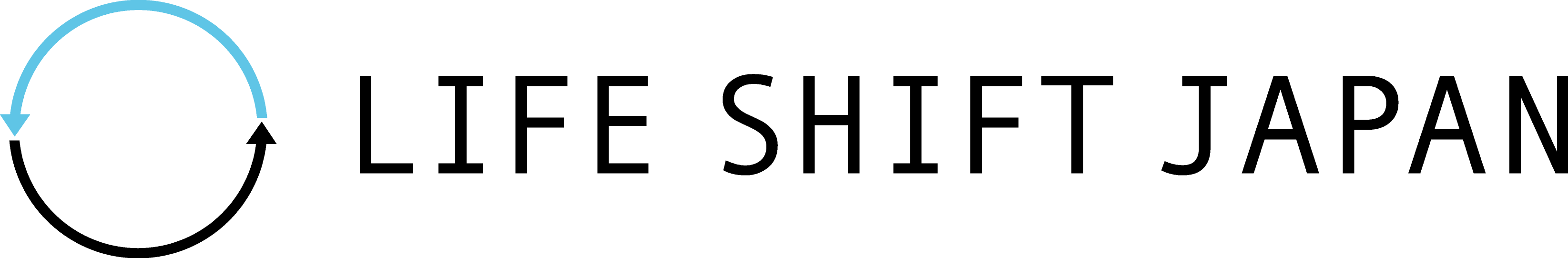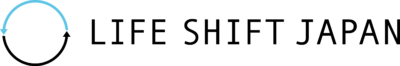本間毅さん(No.84)/HOMMA, Inc. Founder & CEO
■1974年鳥取生まれ。中央大学在学中に起業。1997年にWeb制作・開発を手がける「イエルネット」設立。ピーアイエム株式会社(後にヤフージャパンに売却)の設立にも関わる。2003年ソニー株式会社入社。ネット系事業戦略部門、リテール系新規事業開発等を経て、2008年5月よりアメリカ西海岸に赴任。電子書籍事業の事業戦略に従事。2012年2月楽天株式会社執行役員就任。デジタルコンテンツのグローバル事業戦略を担当。退任後、2016年5月にシリコンバレーにてHOMMA, Inc.創業。米国・カリフォルニア州サウス サンノゼ在住。
■家族:妻、5人の子ども(4男1女)
■座右の銘:“The best way to predict the future is to invent it. (未来を予測する最良の方法は、それを創ることである)”
米国の科学者アラン・ケイの言葉。「僕は鳥取県で生まれ育ち、大学卒業後に地元で堅実な職業に就くというのが、スタンダードな未来予測でした。でも、その予測を採用せず、自分で創ったから、今があります」と本間さん。
学生時代に起業。中学生時代には「社長になりたい」と思っていた
インターネットの黎明期だった学生時代にWeb制作・開発会社を起業し、ソニー、楽天を経て、2016年5月にデザイン性が高く、最先端のテクノロジーを搭載した建売住宅を手がける「HOMMA」をシリコンバレーで立ち上げました。「HOMMA」設立までずっとIT畑でしたが、「建築」や「住宅」とはゆかりが深いんです。父方は京都で十代以上続いた宮大工の家系。祖父は建築士で、設計事務所をやっていました。母方の祖父は建築資材会社の経営者。父も設備系の会社の会社員です。
経営者の祖父たちと会社員の父。それぞれの姿を見て、中学生になったころには漠然と「社長になりたい」と考えていました。鳥取県の高校を卒業後、大学は迷わず経営学科へ。医師を志望する人が医学部に行くように、経営学科で学べば、経営者になれると思っていました。ところが、入学時のクラスに経営者を目指す人はひとりもおらず、「あれ?」と(笑)。
大学で授業を受けているだけでは経営者にはなれないとわかり、「どうすれば、なれるんだろう」と模索していたときに、商業利用がはじまったばかりのインターネットに出合い、「これは面白い!」と思いました。誰でも情報発信ができ、地球の裏側の情報にもアクセスできるところに大きな可能性を感じたんです。
ほどなくして自分でWebサイトを作れることを知り、開設。これはビジネスにできるのではと考え、大学2年生になったころに、仲間を誘って名刺を作り、スーツを着て営業を始めました。すると、珍しさもあってちらほら依頼をいただいたんですね。名刺の渡し方すら知りませんでしたし、儲かってはいませんでしたが、インターネットという新しい世界で、ロールモデルのない中、自分たちで道を作っていく面白さがありました。

大学で友人たちと。このころから大学にはあまり顔を出さなくなった。
鳥取の親戚たちは大反対でしたよ。祖父もです。経営をしていれば、つらい時もある。祖父自身が経験しているからこそ、心配したのでしょう。大学3年生の時に呼び戻され、「インターネットなんて、わけのわからないものが商売になると思ってるのか。長男なんだから、地元に帰って銀行員になり、結婚して幸せになれ」と一喝されました。話をしてもらちがあかず、実績を見せるしかありませんでした。だから、個人事業主としてやっていたビジネスをどうしても法人にしたかった。仲間が就職活動で抜けていく中、三軒茶屋のバーの2階を借りて、数名の仲間とWeb制作・開発会社「イエルネット」を立ち上げました。22歳の時です。

個人事業主として仕事を始めたころの自宅兼事務所。
学生起業した会社を売却し、ソニーへ。28歳で初めて会社員に
時代の追い風もあり、起業して5年たつと、会社はマザーズ上場目前まで成長しました。主幹事証券会社も決まっていました。4億ほどの投資を受け、社員も50名に増やして2001年末の上場を目指しましたが、バブルが弾け、見送りに。生き残りをかけて縮小路線に舵を切り、2年間格闘した末、28歳の時に会社を売却しました。ゼロからやり直そうと思っていたときに、たまたまソニーからお声がけをいただきました。
ソニー入社にあたり、会社には「起業家としての仕事のやり方を変えるつもりはありません」と言いました。28歳にして初めて会社員になり、果たして務まるのかと身近な人たちは心配したようですが、僕自身に不安はなかったです。いざ入社したら、資金繰りの心配をしなくていいし、大企業には人材も資金もブランド力もある。これだけのリソースがあれば、あれもできる、これもできる。そう考えたら、楽しくてたまりませんでした。
最初の配属先は、出井伸之会長(2003年当時)が前年に設立した組織。ソニーグループのネットワークアプリケーション・コンテンツ・サービス関連事業の総合戦略を立て、推進するのがミッションでした。ここで新規事業をいくつか担当し、動画共有サービスを立ち上げたときにはメディアにも注目されて、ハワード・ストリンガー会長兼CEO(2007年当時)と一緒に発表記者会見に登壇しました。
充実した毎日を過ごしていた入社5年目、転機が訪れました。ヘッドハンティング会社から連絡があり、ある米国系ネット関連企業の日本法人CEOに誘われたんです。グローバルな環境で仕事をしてみたいという思いもあって迷っていたら、どこからかその情報を聞きつけたストリンガー会長からある日電話があり、”You can’t leave.”と。何かやりたいことがあるのかと聞かれ、とっさに”I wanna go to California.”と答えたところ、翌年に米国ソニーへの赴任が決まりました。
妻子とともに33歳で渡米。日本企業の存在感の低さを知り、危機感を抱いた
渡米直後は、語学力の壁にぶち当たりました。日常会話には困りませんでしたが、現地法人のヴァイスプレジデントとして仕事をするのに十分なレベルではありませんでした。周囲とコミュニケーションのすれ違いも起き、仕事人生で一番つらい時期でした。しかし、妻子まで連れて渡米したからには前に進むしかありません。半年間必死で英語を勉強して仕事らしい仕事ができるようになり、2年目からは米国ソニーに新たに立ち上げられた電子書籍部門に自ら志願して行きました。
電子書籍部門では、事業戦略を担当し、ハードウェアについてはもちろん、出版社との交渉、オンラインストアの運営、著作権保護・管理まで電子書籍にまつわることをすべて把握できたのが面白かったです。ひとつの事業カテゴリーの上流から下流までを統合して戦略を立て、実行していく過程でのものの見方や考え方を培うことができ、起業した今もその経験が生きています。
楽天に転職したのは、渡米4年目。楽天が電子書籍事業「kobo」を立ち上げるタイミングでした。会長の三木谷浩史さんから電子書籍事業を手伝ってほしいとお誘いをいただきましたが、僕にとってはソニーですでにやってきたこと。正直なところ、気が進みませんでした。お話を受けさせていただいたのは、楽天がグローバル市場に本気で打って出ようとしており、かつ僕の得意分野であるデジタルコンテンツ事業のグローバル展開はまだこれからだったからです。
米国で暮らしながら、日本企業や日本の人材のグローバルでの存在感が非常に低くなっていることに問題意識を持っていました。日本企業も日本人ももっと海外に出ていかないと、この国はどうなるんだろう。そんな思いがあって、ソニー時代から、米国で起業したいと頑張っている日本の若者たちの支援をボランティアで手伝ったりもしていました。だから、日本の企業である楽天が海外に出て行くお手伝いならば、ぜひやりたいと思ったんです。三木谷さんには「電子書籍に限らず、デジタルコンテンツ事業のグローバル展開を担当させていただけるなら」と率直にお話をして、米国に滞在したまま楽天に入社しました。

役員合宿で谷川岳に登った時に三木谷氏と。三木谷氏は「HOMMA」設立を個人的にも応援してくれた。
「もう二度と起業しない」という決意を覆した、ふたつの理由
楽天の執行役員を辞し、シリコンバレーで「HOMMA」を設立したのは、41歳の時です。学生時代に起業した会社を閉じたときから、僕は「もう二度と起業をしない」と心に決めていました。最後までやるだけのことはやったという思いがあり、起業したことに後悔はまったくありませんでしたが、多くの方にご迷惑をかけましたし、家族も心配させてしまった。自分に経営者は向いていない、と思ったんです。ソニー入社後もよく「いつ起業するの?」と聞かれましたが、「やりたいことが見つかったらね」とお茶を濁していました。
その気持ちが変わった理由のひとつは、スタートアップが世の中を変えていく力に圧倒され、刺激を受けたからです。ソニー時代もそうでしたし、楽天では執行役員としてグローバルデジタルコンテンツ事業のベースを作った後に事業開発を担当し、さまざまな起業家と会いました。そうした日々の中で、「Uber 」や「AirBnB」といった創業10年も経たない会社が業界をドラスティックに変えていくのを目の当たりにしたわけです。
一方で、それをやってのけているのがどんな人たちかというと、若い人たちばかりです。名だたるスタートアップの経営者とお話する機会もあり、もちろんどの方もユニークですごいのですが、「宇宙人」というわけじゃない。それで、僕にも何かができるんじゃないかと思ってしまったんです。
もうひとつ、大きな理由があります。やりたいことが見つかってしまったから、です。米国で10年ほど暮らし、住宅事情が良くないことがずっと気になっていました。とくに僕が住んでいるシリコンバレーでは2億円を出しても、築年数100年や50年の水漏れがする家しか買えないということが珍しくありません。土地が高いからでもありますが、そもそも米国の住宅は約9割が中古物件で、新築は1割ほど。米国の人たちは古い家を改装して住むことを当たり前だと思っています。
事情を知るうち、新築物件の約8割を占める「建売住宅」の作り方が古いために、米国の住宅産業はイノベーションが起きにくい構造になっていることが見えてきました。日本のシステムキッチンやユニットバスのようなものがなく、職人がすべてを現場で作る非効率な工法のため、日本で1年あれば建つ住宅も、米国では2〜3年かかるのがスタンダードです。また、「スマートホーム」という言葉を頻繁に耳にする時代にもかかわらず、IoTやAIの導入は購入者任せ。米国の建築業者は住宅を建てるだけで、テクノロジーに関心がありません。
シリコンバレーにはAppleもGoogleもTeslaもあって、テクノロジーによってイノベーションが起きているのに、家だけは100年前のまま。なぜだろうと不思議でしたが、その理由は「変えられる」ということを知らないから。一方、僕は日本の住宅のクオリティを知っていて、日米両方で暮らし、仕事をしてきた経験があり、ITの世界でやってきたバックグラウンドもある。本間家の「血」で、住宅への思い入れもひと一倍ありました。これらの点と点をうまく結びつければ、米国の住宅は変えられる。そう考えたんです。
40代からの起業はシリコンバレーでは遅いほうかもしれませんが、やりたいことがあるのなら、年齢は関係ないはずです。むしろ、住宅には「金融」「不動産」「ホスピタリティ」といったさまざまな要素が混じり合っているので、人生の経験を重ねた今だからこそようやくチャレンジできるようになったと言えます。ただし、それだけでは起業には踏み切らなかったでしょう。僕には妻と5人の子どもがいますし、会社には何の不満もない。おまけに、「自分は経営者に向いていない」という思いを密かに引きづっていました。それにもかかわらず、やりたくなってしまったのは、「人の役に立てる」と思ったからです。米国の住宅を変え、人々の生活のクオリティが上がれば、米国の役に立てる。それをひとりでやるのではなく、日本企業とも一緒にできれば、日本の人たちがグローバルで活躍するきっかけにもなって、日本の役にも立てる。そう考えると、いてもたってもいられませんでした。
白状しますと、それでもどこかにためらいがあったんです。そんなときにちょうど、僕のことをよく理解してくださっている方にプライベートで会う機会があり、ふと起業の話をしたところ、「なぜやらないの?」と言われ、背中を押されました。その方はエンジェル投資家として「HOMMA」の創業期を支えてくれ、今は取締役として経営にも加わってくれています。
1回目の起業との違いは、自分の弱さを認め、仲間の力を借りられるようになったこと
「HOMMA」設立から4年。第一段階として、築50年の住宅を当社オフィスとしてフルリノベーションした実験住宅「HOMMA ZERO」が2018年1月に完成。2020年6月には新築のプロトタイプ住宅「HOMMA ONE」を株式会社サンワカンパニー、パナソニック株式会社ライフソリューションズ社など10社の日系企業とコラボレーションして建てました。

2020年6月に完成した「HOMMA ONE」。ネットの死角をなくし、あらゆる場所でストレスなくリモートワークができる。
次は、18戸のタウンハウス「HOMMA X」が2121年中にできあがる予定です。そこからが本番。コミュニティが生まれることによるスケールメリットを活用し、セキュリティやメンテナンスなどのサービスをサブスクリプションで提供することも目指しています。
「HOMMA」を始めて今日まで、紆余曲折もありました。何度かビジネスモデルの軌道修正も必要でしたし、「HOMMA ONE」が完成し、僕たちが作った家をようやくお客さまに広く見てもらえるという段階で新型コロナウイルス感染症の影響が拡大。当然、しんどいです。でも、光はいつも差し込んできています。コロナ禍により、世界中の多くの人たちが暮らしや住まいを見直しはじめていることも、僕たちにとってはチャンスです。
例えば、IoTによって地方を活性化する「スマートビレッジ」。農林水産省や環境省による再生可能エネルギーの導入や民間による農業改革などが先行していますが、僕はこれを「住宅発」でできないかと考えていました。地方移住に興味はあるけれど、都会の快適な暮らしは捨てがたいという人も多いはずです。そういう人たちに、デザイン性が高く、テクノロジーを搭載した家を提供し、「ビレッジ」を作ってコミュニティ単位で快適な環境を作る。そうすれば、都会でのライフスタイルを大きく変えることなく、港区の半分の家賃で自然に囲まれた生活ができ、移住を選ぶ人も増えるのではないでしょうか。そのアイデアを最近話したところ、日本企業との提携によるプロジェクトがすでに動き始めています。予想以上の反響に驚いていますが、これもコロナ禍で「本当に幸せな暮らし」を追求する動きが加速されたからだと思います。
もちろん、まずは米国で結果を出すのが先ですが、住宅というのは建てるのにある程度時間がかかり、「ビレッジ」となるとなおさら。今から始めておいてちょうどいいくらいです。そう考えると、「住宅」の「スタートアップ」は一見成立しないように思えますね(笑)。でも、短期間でのイグジットを目指すのがスタートアップじゃない。イノベーションを起こすのがスタートアップだと僕は考えています。

2018年のカリフォルニア国際マラソンで初めて「サブスリー」を達成。年に数回はフルマラソンを走る。
起業はマラソンのようなもので、この先もつらいことは必ずやってくるでしょう。マラソンは、ゴールに近づくほどつらい。一回目の起業では、もう走るのはこりごりだと思いました。でも、今はつらくても走り続けられます。一回目の起業との違いは「何のために走るか」。一回目は結局、自分のことしか考えていませんでした。社長になりたい、お金持ちになりたい、有名になりたいと。限界がやってきたのも当然でした。自分のことしか考えていないと、誰かと手を携えることはできませんから。
「自分は経営者に向いていない」という思いは、今も払拭されてはいません。相変わらず、ダメです。ただ、昔はそれが言えなかった。自分の弱いところを認めたくなくて、人にきちんと相談できず、無理をしていました。でも、今は変な意地を張らなくなりました。自分の苦手なこと、得意なこと、すべてを仲間と共有して、力を借りられるようになった。二回目の起業で能力が格段に上がったとは思えませんが、経営者としてのものの見方、考え方が少しは身についてきた気がしています。それに、「経営者に向いているかどうか」はもう僕には関係ありません。やらなければいけないし、やりたいから、やる。それだけです。
(取材・文/泉彩子)