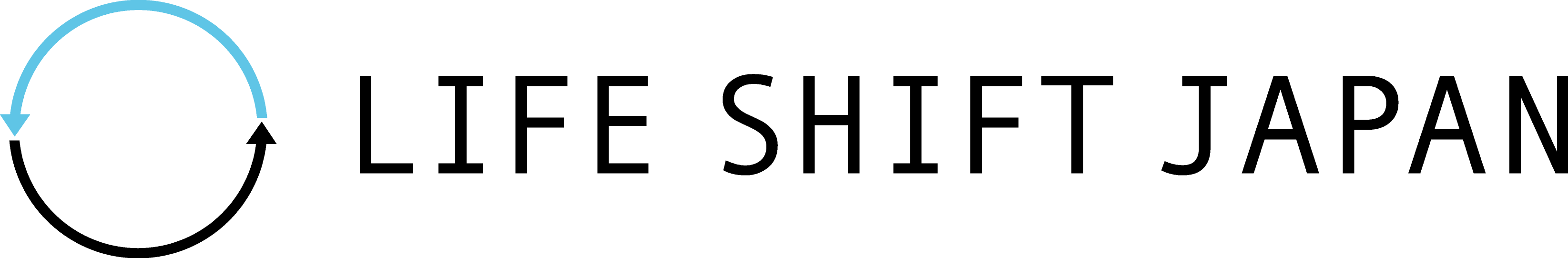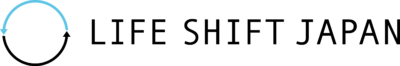「人材輩出企業」という期待と可能性
豊田義博
ライフシフト・ジャパン株式会社 取締役CRO/ライフシフト研究所所長
クエスト・コミュニティとベース・コミュニティ
「私の最初の居場所がFAMでした。メンバーと休日に花火大会に出かけたり、民泊したりしました。気のおけない本当の家族のような存在でした」
荒木さんのインタビューでのコメントです。飯島さんも「FAMには本当に助けられていましたから」と語っています。FAMILYの略語であるこのFAMというシステムは、同社の大きな特徴です。荒木さんのコメントにある通り、キュービックのメンバーにとっての「居場所」になっています。仕事をする、という共通の目的がある職場のメンバーとは別に、一緒にいること自体が心地いい「家族のような存在」が、会社という組織の中に確約されているのです。
コミュニティは、「ともに実現したい共通の目標がある、目的共有の仲間としての性質」を持ったクエスト・コミュニティと、「ありのままでいることができ、困ったときに頼ることができる安全基地としての性質」を帯びたベース・コミュニティとに大別することができます。そして、こうしたコミュニティへの所属が、キャリアの見通しを明るくすることが証明されています。その見通しが最も開けているのは、ベースとクエスト双方を有したコミュニティに所属している人。しかし、そういう人は1割強しかいないそうです(「マルチリレーション社会」2020 リクルートワークス研究所)。
家族主義という言葉でも言い表されていたかつての日本の会社は、ベース&クエスト・コミュニティでした。会社の成長を皆が願い、そして支える。そのメンバーとは仕事の場だけではなく、オフタイムである休日の交流もある。私は、日本の会社らしいとはいえないリクルートという会社に80年代初頭に新卒で入社しましたが、当時のリクルートもまさにそのような会社でした。仕事の後に飲みにいくのはもちろんのこと、休みの日にもよくどこかに遊びに行っていました。会社のメンバーと旅行に行った回数も数えきれないほどあります。70年代、80年代の日本の会社にはまったく珍しくない光景でした。
そのベース性は、バブル崩壊を契機として始まったリストラ、成果主義シフトなどによって瓦解しました。その状況を取り戻そうと、一度は廃止した寮や社宅を新たに作ってみたり、会社主催の運動会を実施してみたり、といった取り組みも一部では行われていますが、ベース性が往時に戻っているという話は残念ながら聞くことはありません。
しかし、往時においても、会社で毎日仕事をしている同じ部署の人、つまりはクエスト・コミュニティのメンバーと、仕事帰りや休みの日に遊びに行く人、つまりはベース・コミュニティのメンバーとは、完全に重なっていたわけではありません。クエスト・コミュニティへの所属は、配属、異動などの公式な辞令によってなされるわけですが、その部署自身が、部署のメンバー全員にとってのベース・コミュニティとなっている、というようなことは稀でした。ベース・コミュニティは、非公式に形成されていたのが大半。同期入社のつながりであったり、以前の部署のメンバーとだったり、同じ趣味趣向の集まりであったり(会社によっては、クラブや同好会のような形で制度化されていました。最近は一部の会社で復活しているようです)。
つまり、非公式ながらも、大半のメンバーが、何らかのベース・コミュニティに所属していた、というような奇跡的な状況を、当時の日本企業は生み出していたわけです。では、それを奇跡的ではなくするにはどういればいいか。そのひとつの解が、ベース・コミュニティも公式なものとし、全員が常にベース・コミュニティとクエスト・コミュニティに所属している状態を作る、という施策。キュービックのFAMは、その好例。特に、同社は学生インターンが半数を占めるような若手=キャリアの短い人がとても多い会社ですから、ベース・コミュニティを公式なものとするという施策は、人材育成の観点からも極めて有効だと言えます。
長期インターンシップが社会を変える
新たなクエスト・コミュニティへの参加機会を開いている、という点もキュービックの特徴です。次なるテーマを探索する全社的な横断プロジェクトの定常化、一段上の仕事機会に挑戦できるキャリアフライト制度は、個人が自身の想いに気づき、新たなチャレンジを思い立つ「シフト」の機会を提供している“ヒト・ドリブン”なものです。
インターンシップの活用も、その文脈でとらえることができるでしょう。自身の将来を想い、自身の可能性を広げたいと考える大学生に、リアルな就業の機会を提供する。それも、社員数よりも多い数の学生を。学生が十分な戦力になるビジネスモデルであったからであり、ローコストで調達できるという側面ももちろんあるでしょうが、いくら優秀な学生が採用できるといっても、100人を優に超えているインターン生にコミットすることは生半可なことではありません。キュービックという“ヒト・ドリブン経営”の象徴が、このインターンシップ活用にあるといってもいいと思います。それは、任せている仕事のレベルからも明らかです。荒木さんや飯島さんの例にあるように、採用活動のリーダーになったり、マージした企業のPMIのリーダーになったり。このように一人ひとりを信頼して託し、任せることが、本人の劇的な成長、自身の想いへの気づきをもたらすのです。
この仕組みを、自社内にとどまらず、事業として社会全体に広げていこうという志にもエールを贈りたいと思います。1990年代後半、就職協定が廃止された頃、私はリクルートの新卒就職情報誌の編集長の職に就いていました。ようやく訪れた自由化の機会を活かし、定められた短期間に企業と学生が面接という限られた機会だけでお互いを見極める「集団お見合い」のような就職活動から、時期を選ばす、学生と企業がいろいろな形で出会う「自由恋愛」のような就職活動へと変えていきたいと考えていました。しかし、それから20年以上たった今も、仕組みは大きくは変わっていません。当時から期待していたインターンシップは広がりましたが、その大半は会社説明会に毛が生えた程度のもの。就職活動が単に早期化しているにすぎません。就業体験型の長期インターンシップが市場に浸透し、キュービック同様に多くの学生に働く機会を提供することは、この不毛な構造を打破する起爆剤になるはずです。インターンシップを、自社の社員となる人材の早期発掘の機会としてではなく、就業体験を通して学生それぞれが自身の想いに気づく機会として捉えられている会社は、“ヒト・ドリブン経営”をしているに他ならないのですから。
「ヒト・ファースト」が変身資産を高めていく
こうした一連のマネジメント施策の原点が、代表・世一氏の高校時代にあったのかもしれない、という点も、とても興味深いものです。世一氏が通った浦和高校は、旧制一校にあたる首都圏でも屈指の公立進学校ですが、同校は勉強、行事、部活いずれにもフルコミットさせることで有名。世一氏のインタビューページの写真には「少なくとも三兎を追え」というフレーズが記されています。複数のコミュニティに所属し、それぞれの場で目的実現のために英知を結集する。それぞれのコミュニティでの経験が相互に影響しあうことで、生徒たちは自己発見、自己確立を果たしていく。この発達モデルは、高校だけに機能するものではなく、大学においても、そして社会人なってからも有効なものです。
しかし、こうした仕組みは、それだけでは機能していない。キュービックのコア・バリューである「ヒト・ファースト」が、望ましい行動規範という形でマネジメントの場に浸透しているからこそ、この仕組みが生きるのでしょう。それは、他社から転職してきた人が異常とまで感じる「評価や目標設定にかける時間の長さ」に象徴されています。ヒトにもっともっと生き生きとしてほしいと想うからこそ、そのヒトのことを深く考える。それは評価や目標設定といったマネジメントテーマに限らない。今流行りの1on1はキュービックでは日常になっているでしょうし、FAMの家長は、自身のFAMメンバー一人ひとりのことを想い、働きかけていることでしょう。そして、ヒト・ファーストは、他者を思うだけではない。自分というヒトに対して想いを馳せる内省の時間も大切にしています。その象徴は月に一日、業務を停止して自分について振り返る「コアデー」というシステム。こうした時間は、自身の変身資産の棚卸し、自覚に、ひいては次のアクションへとつながります。変身資産が増えるエコシステムが形成されています。
会社という大きなコミュニティの中に、多様な小コミュニティを生成させ、メンバーが複数のコミュニティに所属するシステムを組み込む。そして「ヒト・ファースト」というコア・バリュー=行動規範をドライブに置く。これがキュービックという会社のカルチャーの中枢構造です。真似が出来そうにも思います。しかし、転職組が異常とまで感じるヒトへの想いは、そんなに簡単に真似できるものではないでしょう。その想いの原点は、おそらくは、代表・世一氏の原体験の中にあります。それは学生時代に学習塾で働いていた経験ではなかろうか。生徒たちと向き合い、深い洞察を通して一人ひとりの個性や特性に気づき、それぞれに適切なスイッチを押してあげることで、それぞれが劇的に成長していく経験をされたのてはないか。そのような経験を通して、世一氏はヒト一人ひとりが誰しもがもつ大きな可能性に目覚めたのではないか。憶測の域を超えません。でも、何らかの経験を踏まえた信念がないと、異常とまで言われるほどのヒト・ファーストにはなりえません。そして、世一氏と深く交わった生え抜きメンバーの中には、世一氏に匹敵するレベルでヒト・ファーストの精神を内在する第二、第三の世一氏がすでに生まれているようにも思います。そんな彼ら彼女らが中核メンバーとなったときに、「よくて30点」という辛口の評価をした世一氏の点数は跳ね上がるかもしれない。ですが、ヒト・ファーストな精神を携えた第二、第三の世一氏には、外に飛び出して、第二、第三のキュービックを創ってほしい。そういう人材輩出企業となってほしい。インタビューが終わった後に、そういう期待と可能性を抱きました。

メンバーシップ型雇用の未来
大野誠一
ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役CEO
ジョブ型雇用が大流行です。
COVID-19によって強制的に広がったテレワークをきっかけに、これまでの労働時間を主とした労務管理からアウトプットや成果を重視した評価に変えなければならない。そのためには、長年続いて来た日本特有のメンバーシップ型雇用から欧米で主流といわれるジョブ型雇用への切り替えが必要だといわれています。日立、富士通、KDDI、資生堂などが次々にジョブ型の導入を決定。猫も杓子も状態の様にも見えます。
労働政策に詳しい濱口桂一郎氏(労働政策研究・研修機構 労働政策研究所長)は、ジョブ型導入を検討している企業は3つに分類できると指摘しています。①グローバル企業で国内外の人事制度を統一しなければならないと覚悟を決めた会社、②かつて失敗した成果主義のリベンジとしてジョブ型導入を検討する会社、③考えもなしに踊っている会社。
メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へという課題は、昭和の時代から繰り返し議論されて来たテーマですが、これ程までに急速に具体化する状況は、かつてなかった事でしょう。まさにコロナによって、日本特有のメンバーシップ型雇用の命運が尽きようとしているかの様です。
そんな中、「ヒト・ファースト」をコア・バリューとするキュービックの世一社長は、「メンバーシップ型を好む」と明快に語ってくれました。会社にとって最も大切なことは「カルチャー」であり、「カルチャーに共感する人が集まるのが本来の会社のあるべき姿」と語る世一社長は、「FAM」などのユニークな制度を通じて、メンバー同志の関係を、仕事を超えたコミュニティにしていこうとしています。それは、21世紀の「新しいメンバーシップ型雇用」を創造しようとするチャレンジなのかもしれません。
私たちは今、いつの日か「Before」と「After」の区切りの年と語られるであろう「2020年」という時代を生きています。単に時代遅れと切り捨てられそうな古びた服を捨てて、目新しい既製服を買い求めるのではなく、素材から縫製の仕方までを自分自分で考え抜いて、世界でたったひとつのオリジナルをつくり出す事が大切なのです。