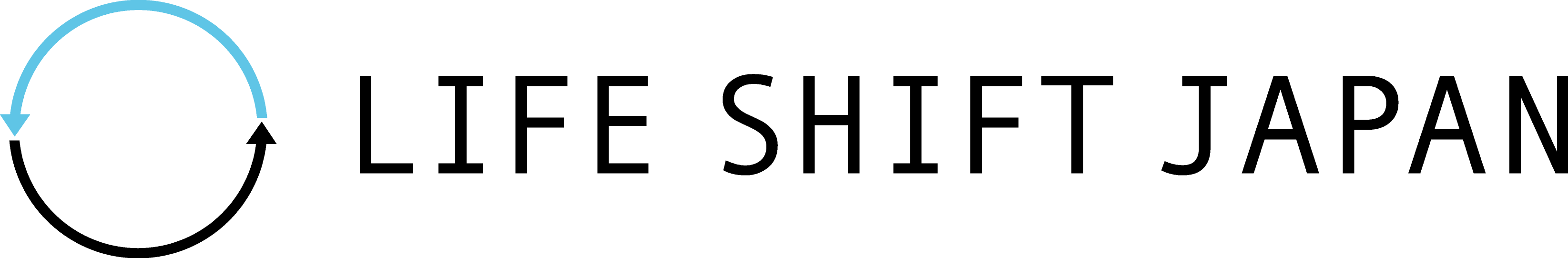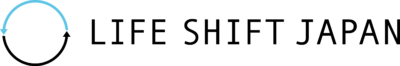CIとカルチャーはコインの裏表
豊田義博
ライフシフト・ジャパン株式会社 取締役CRO/ライフシフト研究所所長
コロナがもたらした土づくりの危機
週に何回か、交代でランチを作り、みんなで食べる。月末の金曜日にはオフィスでパーティーを開き、メンバーだけではなく、ビジネスパートナーや家族など大切な人々を招いて感謝の意を表す。食事はもちろんみんなで作る。そして、年一回の「焚火合宿」。目的は、焚火を囲むことのみ。みんなで火を起こし、火を眺めながら、普段は話せないような深い話を交わしていく。
New Standardの経営の三要素、CI、カルチャー、マネジメントデザイン。序列や優先順位はないけれども、難しいのはカルチャー=土づくりだと代表の久志氏はインタビューで語ってくれました。そして、カルチャーを育むために同社が大切にしていたのが、自炊ランチ、月末パーティー、焚火合宿。対話するにとどまらず、食事を作ったり、一緒に火を起こすなどの共同体験を通じて相互理解を深め、さらにNew Standardが大切にしているものの考え方や行動様式、つまりはCIの3構成要素の一つであるBI=ビヘイビアアイデンティティが共有されていくという仕組みです。そして、BIは、「この世界は、もっと広いはずだ」というMI=マインドアイデンティティを実現するためのもの。また、BIと評価制度をリンクさせる仕組み、BIをメンバー一人ひとりの行動につなげていくための施策など、マネジメントデザインの刷新もなされています。CI、カルチャー、マネジメントデザインが分かち難く結びついているわけです。
その土台に当たり、作り上げるのが難しいと久志さんも語っていたカルチャーを大きく揺さぶったのが今回のコロナ禍です。カルチャーを育む大切な場だった対面でのコミュニケーションや共同体験ができなくなってしまったのですから。単に働く場ということではなく、集まる意味を持っているオフィスに毎日来ることができなくなったことは、NEW STANDARDにとっては大きな打撃なのではないか。ビフォーコロナのときのカルチャー=土壌のつくり方とは全く違うウィズコロナ、アフターコロナの時代の土づくりは見えてきているのだろうか。気になるポイントでした。
組織文化とは「らしさ」である
しかし、久志さんの口から出てきたのは「割と問題なく移行できたのではないか」という言葉でした。新たな土づくりに力を入れ、月末パーティーのオンライン化、オフィス再編プロジェクトなどの改革を走らせ、BIで掲げた行動指針=NO SPECTATOR(傍観者であるな、当事者であれ)を前面に押し出し、メンバーみんなが土を耕す、土壌づくりに主体的にコミットすることを求め、メンバーはそれにしっかり応えているのだそうです。その結果として新たにどんな土壌ができるかはわからないけれど、みんなで違う土を作っていくという壮大な変革が、どうやら順調に進んでいるようです。
改めて。カルチャー=文化とは何でしょうか。Wikipediaには「人間が社会の構成員として獲得する多数の振る舞いの全体のことである。社会組織ごとに固有の文化があるとされ、組織の成員になるということは、その文化を身につける(身体化)ということでもある」とあります。また、組織文化という概念についてはE.シャインはじめ多くの研究者が定義していますが、それらを概観すると「組織のメンバーの間で共有されている信念や価値観や行動様式」とまとめることが出来そうです。
そうした文脈や定義を踏まえて。私は、組織文化とは「らしさ」だと考えています。会社には「らしさ」があります。いかにもこの会社らしい製品、とか、なんともあの会社らしい人、とか。それぞれの会社には、それぞれの会社なりの「らしさ」がある。いいとか悪いとかではなく、それぞれの会社固有の「らしさ」がある。そして、「らしさ」の原点は、その会社を立ち上げた人たちの「想い」です。社会のために、誰かのために何かをしたい、とか、自分たちはこうなりたい、こうありたい、といった「想い」が起点となり、アイデアや行動が生まれ、やがては製品やサービスとなっていく。また、その「らしさ」が外部の人間からも明確である会社と、そうではない会社があります。明確でユニークな「想い」から、明確でユニークな「らしさ」が生まれるのです。
「らしさ」は、明文化されているビジョンやミッションと重なることもありますが、そうではないケースもままあります。目指したい姿と実態は、往々にしてずれています。組織が大きくなればなるほど、その度合いは増していく傾向にあります。そして、その「ずれ」を矯正するために、様々な会社が組織改革を断行する。そしてその大半は失敗に終わる。良くも悪くも「らしさ」は「らしさ」。思うように変えられるわけではありません。
コミュニケーション改革の目的はカルチャーの再創造
今回のコロナ禍によって、企業内のコミュニケーションのありようは激変しました。その変化に対して、どんな会社も何らかの対応に迫られ、施策を講じています。その主な動機は「ビフォーコロナの時のコミュニケーションの質を保とう」というものでしょう。会社とはつまるところ人の集まり、会社はコミュニケーションでできている、といっても過言ではありませんから、この取り組みは会社の未来の生命線を握っているといえます。オンラインコミュニケーションの浸透など奏功している施策もありますが、そのオンラインコミュニケーションにも課題を大きく残るなど、今はまだ変革の渦中です。
では、コミュニケーション変革は、なんのためなのか。一番大切にしなくてはならないものは何なのか。久志さんは、カルチャーだと即断したのでしょう。そして、改めてカルチャーとは何かを捉えなおし、結果としてどのような土壌の変化が起きたとしても、その土壌は「NO SPECTATOR」と看板に掲げられている行動指針が今と同じないしは今以上のレベルで体現されているものを目指す、と確信したのでしょう。
アメリカの著名なサービスデザイナーの一人であるデイブ・グレイ氏は「文化とは会社のOSである」と指摘していますが、実に適切なたとえです。時代に即した看板に掛け変えても、最新の農法を投入しても、土壌というOSが旧式のままでは変革はできません。そして、文化の起点は、創業者の「想い」。久志さんは、起点である「想い」を言語化した「NO SPECTATOR」という行動指針を中核に据えて、カルチャーの再創造に乗り出しました。そして、行動指針の通りにメンバーの主体性に「賭けた」のだと思います。
そして、おそらく、多くのメンバーは、久志さんからの働きかけを待つことなく、自分で動き出していたのではないか。今回お話を伺ったお二人の話は、そう感じさせるに足るものでした。市原さんは、プライベートでコミュニティを立ち上げています。デザイナーである白鳥さんがいつかは女性向けの事業を起こしたいとおっしゃいました。そのベースにあるのは、「WE CREATE WHAT WE WANT 欲しいものや未来は自分たちの手で創り上げる」という精神。このフレーズは、NEW STANDARD内の標語であり、カルチャーのベースとなっているもの。「NO SPECTATOR」という行動指針とも大きく重なるフレーズです。どうやら、この会社のメンバーは、久志さんが大切にしたいスピリットをすでに内在しているようです。CI=看板とカルチャー=土壌には「ずれ」がないようなのです。まさに「看板に偽りなし」。この状態こそが組織にとって最も望ましい状態であることは言を俟ちません。
アフターコロナのNEW STANDARD?
NEW STANDARDが実現している“ヒト・ドリブン経営”のメカニズムを、Departure Ⅱでご紹介した4つのビジョンのフレームに当てはめながらレビューしていきましょう。
創業時にはTABI LABOというサービスのコンセプトに、そして昨年のリブランディングにおいてはMIに込められた「社会への想い」。BIや「WE CREATE WHAT WE WANT」という標語に込められた「メンバーへの想い」。クリエイター集団ならではの表現力を伴って発信されるこうした「想い」は、火種を起こし、狼煙を上げることで、カスタマーはもちろんのこと、それらに強く「共感」する仲間を呼び集めます。「想い」でつながり、その「想い」を内在化する仲間は、やがてはカルチャーを体現するだけではなくカルチャーを再創造していく主体者となっていきます。また、新たなスタンダードを生み出したいという「想い」の視界は社会に開かれた「社会企業」のもの。仲間一人ひとりにも、その一員として、世の中に新たな価値観を届け、一人でも多くの人に夢中になってほしい、という「市民」意識が芽生えます。
仕事へのコミットの基本は「NO SOECTATOR」。職種や役割に規定されることなく、また、メンバーそれぞれが、自身の気持ちのあるがままに、自身が心底楽しい、嬉しいと思えることにコミットして欲しいというとてもポジティブな行動指針。一人ひとりを信じて託すのはもちろんでしょうし、この指針が個人の自立&自律につながるのは、市原さんの「自分を常にアップデートし続けられることこそが大切(であり安定)なのだ」という発言からも明らかです。
そして、「NO SOECTATOR」という指針によって、あるいはその指針を共有している仲間との対話を通して、ヒトは自分の中にある「想い」に気づいていきます。気づいたならば、何かを起こさずにはいられない。それは決して強制的なものではなく、間違いなく自発的なものです。そして、自らの変身資産を高め、活かして主人公となっていく。市原さんが、プライベートでコミュニティを立ち上げたように、白鳥さんが新事業を構想しているように。身体化したカルチャーが、ヒトを新たな行動へと駆り立てるのです。アップデート、つまり変化し続けることにより自身が高まっていく、「変身資産」が増え続けるエコシステムがそこには生まれています。
「同じ釜の飯」を食することを大切にしてきたNEW STANDARDは、強烈な運命共同体です。そして、「自炊ランチ」をはじめとする対面でのコミュニケーションや共同作業とは異なる形でのカルチャー再創造を模索しています。OMO(Online Merge Offline)というビジネスの潮流を自社のカルチャー醸成に活かしていく、というチャレンジ。アフターコロナのコミュニティコミュニケーションのNEW STANDARDが生まれるかもしれない、、、そんな可能性を感じています。

ヒッピー文化とミレニアル世代
大野誠一
ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役CEO
ミレニアル世代(1981年以降に生まれ、2000年以降に成人を迎えた世代)は一般的に、情報リテラシーが高く、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを求め、仲間とのつながりを大切にして、社会貢献性の高い仕事を志向する、と言われて来ました。
NEW STANDARDは、まさにミレニアル世代の価値観をリアルな形にした会社です。
そして、そのベースとなる考え方は「ヒッピー文化」と強く共鳴しています。
「Burning Man」(ヒッピー文化を発祥とする大規模イベント。毎年の8〜9月にアメリカ・ネバダ州のブラックロック砂漠に数万人に集まり、約一週間に渡って多様なコミュニティを形成する。2020年は、オンラインで開催)にも参加した経験を持つ久志さんは、「Burning Man」のコンセプト「NO SPECTATOR」を会社の行動指針の一環に置き、その想いに共感し、実践しようとする仲間を集め、仲間と共に狼煙をあげようとしています。
「NO SPECTATOR=傍観者になるな、当事者であれ」を指針に、考え、行動するNEW STANDARDのメンバーは、圧倒的に自立&自律している様に見えます。
「ヒッピー文化」と「ミレニアル世代」をキーワードに語られる会社の姿は、古い日本企業とは全く違う別世界にいる様な印象を感じさせます。一方で、「C I」「カルチャー」「マネジメントデザイン」を軸とする経営スタイルは、とても正攻法のマネジメントの実践であり、昨年、実施されたリブランディングで定義された「CI」は、その言葉の一語一句、デザインの細部まで、徹底的に吟味されています。
そして、久志さんがヒッピー文化から学んだという3つの精神、「Do It Yourself精神」、「見えないものを信じる力」、「SDGsにつながる環境への関心」は、これからの世界のトレンドを表している様にも思います。
未だにミレニアル世代やさらにその下の「Z世代」のマネジメントに困惑しているカイシャが数多く存在する中、そんな「フツーのカイシャ」からは、NEW STANDARDは別世界の存在に見えるでしょうか?
もしかすると、NEW STANDARDの経営スタイルがまさに「NEW STANDARD=新しい標準」となる時代は、すぐそこまで来ているのかもしれません。