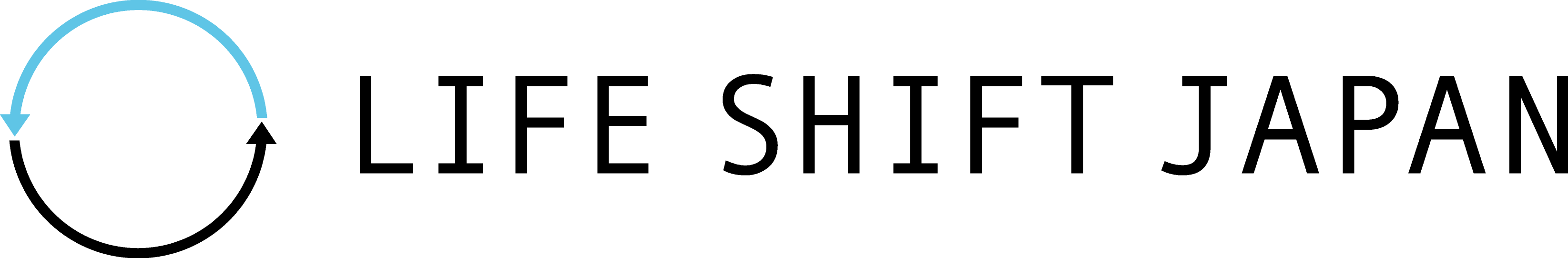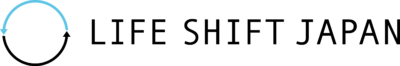コミュニティとチームのハイブリッドは成立するか?
豊田義博
ライフシフト・ジャパン株式会社 取締役CRO/ライフシフト研究所所長
日本の会社も「コミュニティ型経営」だった?
ソニックガーデンが目指しているのは「コミュニティ型経営」。代表・倉貫氏は、似ていながらその対極にある「チーム型経営」との対比から、自社のマネジメントの方向性を明確に語ってくれました。ソニックガーデンのユニークさの底流にある組織ビジョンが実によくわかりました。また、私たちが掲げている“ヒト・ドリブン経営”のひとつの究極の姿を見たようにも思います。「納品のない受託開発」というユニークでビジョナリーなビジネスモデルをベースに明確に社会への想いを発信しています。普通の会社がやっているような管理はナシで社員は純粋に想いだけでつながっています。完全にオンラインベースでのコミュニケーション(この記事の扉の写真は、ソニックガーデンのオンライン上のオフィス。Remottyという独自開発ツールです)でありながら、「ザッソウ(雑談+相談 倉貫氏の造語)」文化が醸成され、対話を通じてヒトは新たな自分を見つけ、変身資産を増やしています。そして、西見さんや高木さんの考えや活動からは、自分たちが生み出したモノ、大切にしているモノを、エンジニア社会に伝えていきたい、会社を超えてつながりたい、という市民意識=シティズンシップも見て取れました。
しかし、話をお聞きしながら、素朴な問いが頭をよぎっていました。日本の会社も「コミュニティ型経営」だったのではないか、と。
「チーム型経営」と「コミュニティ型経営」の違いをおさらいしましょう。以下の表は、倉貫氏がご自身のブログに掲示しているもの。とても分かりやすく、両者の違いを対比させています。

インタビューでのやり取りにもあるように、大半の起業家が「チーム型経営」を目指し、実行に移しています。ゴールを設定し、機動性の高いリソースを獲得し、投入し、市場での戦いに挑む。「戦争」に勝つか負けるか。勝てば次の戦いに進むし、負ければ撤退=解散です。欧米等のグローバル企業の多くは、より純度の高いチーム型経営を行っています。会社という単位では「終りと解散がある」わけではありませんが、事業という単位でみれば、より徹底しているといえるでしょう。
しかし、日本の大企業は、意外とあきらめが悪い。アメリカ流の「選択と集中」を見習い、部門買収などもずいぶんと活発になりはしましたが、成果がなかなか出ない事業に見切りをつけないケースはまだまだ見受けられます。分の悪い戦さだから撤退する、という考え方を良しとしない風土があります。欧米のようにドラスティックなリストラ=人員整理をやりにくいから、ということも大きな要因でしょうが、戦っている人たちの想いを無下にしたくない、という温情もある。事業よりもヒトを優先しているようにも見えます。
また、グローバル企業やベンチャーの中にも、ビジョンを大切にし、価値観・理念への共鳴で集まっている「コミュニティ的なチーム」という会社が存在します。スキルよりは人間性を重視し、即戦力よりは将来のための人材を採用している「チーム」もあります。最近では「安心と安全」を大切にしている「チーム」も散見されます。たぶん、日本の大手企業は今もこんな「コミュニティ寄りのチーム」なのだと思います。そして、高度成長からバブル崩壊までの日本企業は、家族主義を標榜し、雇用を守り、社会とともに歩む「コミュニティ型経営」を目指していたのではないかと思うのです。
有形報酬をインセンティブとして機能させることの是非
コミュニティ型とチーム型、この両者の違いは、有形報酬についての捉え方にも表れます。その戦いにどう貢献したのか、という短期志向、結果志向であり、メリハリをつけることを重視するチーム型の有形報酬に対して、コミュニティ型のそれは、より長期なものになる。この背後には、ヒトを何によって動機づけるのか、という視点の違いが浮かび上がります。倉貫氏がインタビューで語ってくださったコメントを再掲します。
外発的動機の源である金銭や地位などの有形の報酬には、強烈なインセンティブ効果が見込めます。それを一切活用しない、という潔さ。長期志向であることが明確に浮かび上がる発言です。そしてそこには、人間に対するしたたかな洞察があるのでしょう。それは、「ヒトは、お金や権力に目が眩み、目の前の仕事の先にある本来の目的を忘れるものだ」という見立てでしょう。背後には、短期的な有形報酬には、そのヒト本来のありたい姿(BE)や求めるもの(無形報酬)を変容させてしまう悪魔の力がある、という捉え方もあるように思います。
しかし、逆の捉え方をする人もいます。「ヒトは、放っておけば怠ける存在だから、お金や地位という報酬をうまく使って、やる気にさせなくてはならない」という捉え方です。そして、この捉え方の背後には、仕事というモノに対するこんな見立てがあります。「会社の収益を上げるために、ヒトに●●という仕事をしてもらう。しかし、その仕事は面白いものでも楽なものでもないので、それなりの対価を支払って仕事をしてもらう」
前者と後者は、人間をどのような存在とみなすかにおける性善説 vs. 性悪説と対比することもできますが、仕事というものの捉え方が違うことが、その根底にはあります。仕事とは、そのヒトが本来ありたい姿や求めるものを実現するためのものなのか、会社の収益向上のために課された指示・命令なのか。報酬という言葉で言い換えれば、無形報酬を得るためのものなのか、有形報酬を獲得するものか。
ソニックガーデンの人間観、仕事観が前者であることは自明ですが、昭和の時代の日本企業はどうだったのでしょうか。
日本企業の「至福の時」は長くは続かなかった
実は、戦前の日本の企業は、学歴によって仕事やキャリアが規定されていました。今風にいえば格差社会です。中学卒の人は生涯現場で働き続け、少数の大卒者が幹部になるというエリートコースが明確にありましたし、卒業する大学によって初任給には違いがありました。今さかんに議論されているジョブ型にある意味では近い構造だったわけです。また、事務職、技術職が上に見られ、現業職や営業職が下に見られる、といった身分格差的な扱いもなされていました。このように、当時の日本企業は、短期志向のチーム型経営が主流であったのです。
しかし、戦後の労働争議などの動乱を経て、こうした格差は大幅に是正されました。どのような学歴であっても、貢献度にあわせて給与も地位も上がっていく、そして年数とともに貢献度は高まっていく、つまりは年功序列によるマネジメントへと移行したのです。格差社会から平等社会に。同じ年齢なら給料はみな同じ。みんな同じように昇進していく、高卒者でも課長になれる、世界にも類を見ない社会が実現しました。そして、当時のヒトが追い求めていたのは、より豊かな暮らしを実現し、家族に苦労をさせずに養っていくこと。仕事はそれを得るための大切な手段であり、その有望な手段を獲得していた人は、人生の主人公として生き生きとしていたことでしょう。多くの人が望む無形報酬を有形報酬とセットで提供するという理想郷であったというと、言いすぎでしょうか。
つまり、高度成長期の人間観、仕事観、そして有形報酬についての考え方は、ソニックガーデンが志向している前者のものと方向性は同じなのです。半世紀ほど時がたっていますので、その内実にもちろん大きな違いはありますが、大きく見れば同じ立ち位置にいたのです。
しかし、そのような至福の時期は長くは続きませんでした。
発展途上な社会において、多くの人が、より豊かになりたいと思い、仕事を「豊かな生活を手に入れるための手段」として捉えていた60年代の高度成長期から、ドル・ショック、オイル・ショックという変曲点をも見事に乗り越え、日本が「Japan as No.1」と国際社会から評価される80年代初頭には、日本人は一定レベルの豊かさを獲得していました。そして、そのころには仕事は生活を豊かにするための単なる手段ではなくなりつつありました。仕事そのものが面白いか、自分にとって意味・価値があるかということを、つまりは仕事から得られることそのものが目的になるという変化が生まれていました。
しかし、会社勤めをしている多くの人にとっては、自身の仕事内容は「ありたい姿や求めるもの」ではなかった。それは、勤めている会社で何をするかは本人の意志で選べるものではなく、「会社の収益向上のために課された指示・命令」であったからです。ジョブ型ではなくメンバーシップ型であるから、と説明できるでしょうが、タテ社会の傾向が強い日本社会の特徴に起因する部分も大きいように思います。高度成長期にも、もちろんそうであったわけですが、仕事の手段性が低下し、目的性が高まることで、自身がその仕事を主体的に選択していない、ということがヒトの意識を大きく変えていきます。
そして、自身が望むものではなく、会社から課される仕事に従事する人、つまり内発的な動機が得られない状態のヒトにとって意味を増してくるものは有形報酬です。ヒトはより給与の高い大企業に入ることを志向するようになり、昇進昇格に一喜一憂するようになります。給与も昇進昇格も決して大きな差がつくような社会ではなかったにもかかわらず。
スケールを目標に掲げるという市場原理
では、仕事が「会社の収益向上のために課された指示・命令」になってしまうのはなぜなのでしょうか。その答えも、倉貫氏のインタビューコメントの中にあります。倉貫氏は、売り上げや従業員数などの会社のスケールを目標として規定していない、それはコントロールできるものではないからだ、と指摘しています。多くの企業経営者は、売上高や従業員数を数値目標として設定している。しかし、それをしない。倉貫氏が唱える「コミュニティ型経営」の真骨頂は、実はこの意思決定にあります。ビジョンは掲げる。掲げることは自身の力でできるから。しかし、ゴールとしての数値目標は置かない。それは自身の力でできるかどうかはわからないから。だから諦める。
多くの会社は、売上高をコントロールしようとします。一定の利益を上げ、従業員の賃金を確保し、成長・拡大に向けての投資をしていく、といった誰もが構想するストーリーの実現こそが会社を経営することだ、と考えている。そしてその実現のためにさらに細かなストーリーを描き、そのストーリーにあわせて社員に仕事を割り振っていく。株式を公開している企業となれはなおさらのこと。株主に価値を還元していくためには、収益確保が絶対条件であり、また、魅力的なストーリーを作らなくては株主は増えない、という市場原理の中に身を置いています。
この市場原理と「コミュニティ型経営」は、フィットしません。だから、同じように「コミュニティ型経営」をする会社は増えないだろう、と倉貫氏は喝破します。
高度成長期の日本企業も、ある側面から見れば「コミュニティ型経営」をしていたように見えますが、収益拡大を明確に志向していました。しかし、生き残りをかけた戦いをしているという意識ではなく、国全体の勢いに乗っていた状態です。また、一定レベル以上の経営をしていれば多くの企業が拡大できた、という発展途上の社会でもありました。また、株主重視の経営ではなく、社員の雇用を守る、社員の貢献に報いる、という意識でもありました。しかし、そうでありながらも、日本の会社が大切にしていたのは個々人によって固有である内発的動機や、希求する無形報酬ではなく、皆にとって一律である有形報酬であり、外発的動機でした。そしてその傾向は、高度成長期はもちろんのこと、現代にも強く残っているものです。
かくして、自身の心の中の問いは、コミュニティ型とチーム型のハイブリッドはあり得るか、というものへと昇華しました。バブル崩壊から今日まで、多くの日本企業は、本来持っていたコミュニティ型の良さを捨てずに、チーム型の良さを入れ込んだハイブリッドモデルを創ろうとして失敗を重ねてきました。完全にチーム型へと移行した企業もありますし、チーム型に適した人材も多く生まれています。しかし、日本社会は、会社にコミュニディ性を今も期待しています。しかし、ソニックガーデンのような純度の高い「コミュニティ型経営」を多くの会社が目指せるだろうか。“ヒト・ドリブン経営”をモデル化していく上で、とても大きな宿題を頂いた今回のインタビューでした。

『ヒト・ドリブン経営』のエコ・システム
大野誠一
ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役CEO
そこで働く一人ひとりが人生の主人公となって、「人生100年時代」をワクワク生きていける経営モデル『ヒト・ドリブン経営』とは、ひとつの“型”にモデル化できるものではなく、その会社独自の徹底的にオリジナルなエコ・システムを象徴する概念なのだと思います。
ソニックガーデンの取材を通じて、そんな確信めいた想いが湧き上がって来ました。
「納品のない受託開発」というビジネスモデル、「プログラマを一生の仕事にする」というビジョン、ソフトウェア開発の分業化を否定する「顧問プログラマ」という働き方、相思相愛を確認する採用プロセス、一切のオフィスを持たないフル・リモートによる組織運営、「あなたVS私」ではなく「問題VS私たち」を追求する意識形成、そんな会社に集う仲間たち、そんな会社を求めるクライアント…。
ソニックガーデンを形づくるそれらの要素は、どれかひとつを取り外すだけでも、たちまちソニックガーデンではないまったく違う会社に変わってしまう様な、強く結びついたエコ・システムを構成しています。
そして、そのエコ・システムが生まれた起点は「ヒト」です。倉貫社長の「人に合わせて制度が変わり、人に合わせて事業も広がる」という言葉が、まさにこの事を言い表しています。
ソニックガーデンのエコシステムは、徹頭徹尾オリジナルなもので、だからこそ真似をすることができないものです。ソニックガーデンのエコ・システムを構成する要素に魅力を感じて、そのいくつかをつまみ食いする様なことをしても、決してソニックガーデンにはならない。それは、むしろ元の組織のバランスを崩したり、空中分解させてしまう様な危険な行為かもしれません。
ベスト・プラクティスを探し求める発想ではなく、徹底的にオリジナルなエコ・システムを創造すること。それこそが『ヒト・ドリブン経営』実現への道です。『ヒト・ドリブン経営』という経営モデルは、それぞれが目指すビジョンによって、無限のバリエーションを生み出すものなのです。