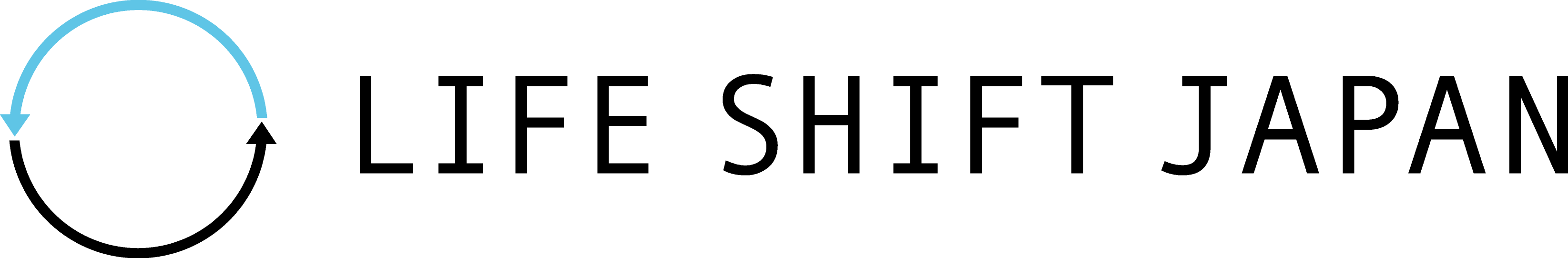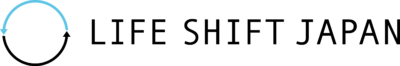平紀和さん(No.83)/スタイリスト
■1964年生まれ、新潟県新潟市出身。1986年、日活芸術学院卒業。「オンシアター自由劇場」の劇団員を経て、1988年よりアパレルメーカー・株式会社聖林公司に勤務。店舗販売を経験後、長く輸入部門を担当した。2008年、スタイリストとして独立し、神奈川県三浦郡葉山町に事務所を設ける。加山雄三さんやテレビ朝日アナウンサー・松尾由美子さんをはじめ多くの著名人のコーディネートを担当。個人のスタイリングや、アパレル企業のブランディングも手がける。2013年に父を葉山の事務所に迎え、株式会社ヴィットリアジンテーゼを設立。2019年に父を看取り、2020年2月より母とふたりで暮らす。ファッション業界でキャリアを築く一方、2005年9月に慶應義塾大学文学部通信教育課程入学。2015年3月に文学部卒業。翌2015年に総合政策学部の3年次に編入学、2018年4月より、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科修士課程在籍。
■家族:母とふたり暮らし。大学生の息子は、卒婚した元妻と世田谷区二子玉川に暮らす。
■座右の銘:「気合いと根性」
「物事を突破する力として、“気合い”というは大きいなと常々感じています。“根性”は家訓です」と鷹揚に笑う。
新潟市の海の近くで育ち、高校時代に『太陽の季節』を読んで葉山の空気に憧れた
スタイリストとして独立した時に事務所を神奈川県三浦郡葉山町に構え、12年になります。2020年春からは4LDKの緑豊かな一軒家に住居と事務所を移し、母とふたりで暮らしています。裏には竹林があり、たけのこ狩りが楽しめるんですよ。この家に引っ越してきたのは新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されたころ。当時は仕事が激減し、眠れない夜も数日ありましたが、たけのこを掘ったり、海沿いを散歩しているうちに、穏やかな気持ちになっていきました。自然の持つ力というのは大きいものですね。

夕刻の葉山公園。相模湾越しに夕日と富士山を望む。
もともとは葉山に地縁はなく、出身地は新潟市です。父は明治大学を卒業後、地元で叔父が営む印刷会社を養子として継ぎ、学生時代に出会った北九州市小倉出身の母と結婚。僕は4人兄妹の3男として生まれました。母は家父長制の影響の残る九州風の子育てで、三男の僕が新しいお菓子の箱を開けると叱られました。海の近くで育ち、小学生の時は牡蠣をとって焼いて食べたり、ワタリガニを捕まえるのが日常の光景でした。
新潟で生まれ育った僕が葉山という地名を知ったのは、16歳の時に小説「太陽の季節」を読んだのがきっかけです。本屋さんで真っ赤な表紙が目に飛び込んできて、思わず手に取ったんです。当時の僕は地元のプロテスタントスクールの高校生。価値観を押し付けるような教育に反発を感じていた時期でしたから、同世代でありながら自主性を持ち、自立している登場人物の姿にカルチャーショックを受けました。
次に「狂った果実」を読むと、一色海岸や森戸海岸といった葉山の地名が克明に書かれていて「どんな場所なんだろう」と想像を掻き立てられました。それで、当時東京の美術専門学校に通っていた次兄に連れて行ってもらったんです。兄のバイクの後ろに乗って流れていく景色を見ていると、茅ヶ崎市周辺の海岸線は新潟市と同じように平坦だけど、鎌倉市から葉山町にかけては起伏に富んでいて、山が見えたと思ったら、海が開ける。変化のある地形に魅了され、なんてドラマチックな場所だろうと強烈な印象が残りました。
上京後、劇団員を経てアパレルに勤務。劇団が社会人としての基礎を作ってくれた
大学受験では慶応義塾大学を志望していました。母方の祖父や叔父たちが慶應出身で、テレビで早慶戦をやっていると母に呼ばれ、物心つかないうちから自分は慶應に行くと思っていました。ところが、必須科目の小論文が苦手で、不合格。浪人もしましたが、あきらめてしまい、上京して映像の専門学校の演劇コースに入りました。子どものころから映画が好きで、小学校の学芸会で脚本を書くなど映画や演劇への関心が強かったからです。

劇団員時代。ウッドベースの後ろ、顔に黒い隈どりをしているのが本人。
卒業後は役者を目指して劇団に入りましたが、最初の5年間は研究生として無給だったんです。日中稽古をして深夜から早朝までアルバイトという日々を1年あまり続けるうちに心も体もくたくたになり、ある日、お客さんの拍手をうれしいと感じなくなってしまいました。そんな日が3日ほど続き、限界を感じて、退団。この先長く続けていくにはと考えて、映画と同じくらい好きだった洋服に関わる仕事をしようと代官山にある「ハリウッドランチマーケット」で働きはじめました。
当時、人気のお店はいくつかありましたが、その中で、「ハリウッドランチマーケット」が一番自分に合っていると感じました。というのも、スタッフがみんな走っていたんですね。この自由で活気のある場所なら、自分が生かされる、自分なら、誰よりもカッコよく走れると思ったんです(笑)。これが、大正解でした。最初はアルバイトでしたが、気づいたことをどんどん提案したところ、社長の目に留まり、お店に入って2週間ほどたったころには、週に1度の幹部ミーティングに呼ばれるように。1年半で副店長になり、5年目には新規店舗「OKURA」の立ち上げに関わり、初代店長を務めました。

代官山「OKURA」の店長を務めていたころに、お客さんと。
大学も出ていなかった自分が実績を出せたのは、劇団での経験が大きかったと思います。僕が所属していた劇団では、会社員の芝居をするなら、フィールドワークをして会社員の動態を研究し、みんなで情報を共有して方針を検討しながら作品を作るといったアカデミックなアプローチで作品を作っていました。それがマーケティングに生きました。
何よりもありがたかったのは、ものづくりの真髄を学ばせてもらったことです。劇団では、俳優だけでなく、大道具係、小道具係、衣装係といったお芝居に関わる人たちみんなが、幕が開く日には感動に包まれていました。全員がそのお芝居を「自分たちの芝居」と言える状態になっている。だから、洋服の世界に入ってからも、どんなものであれ、自分の売るものには誇りを持って売るのが当たり前だと思っていました。劇団が僕の社会人としての基礎を作ってくれたんです。
44歳でスタイリストとして独立。事務所を葉山に構え、二子玉川の自宅から通った
学生時代に英語が好きだったことから、29歳で輸入部門に異動。バイヤーとして、海外代理店との交渉を担当しました。イタリアで新規取引先を開拓し、イタリア人とかかわるうち、彼らの紳士的で知的な立ち居振る舞いに大きな影響を受けました。彼らにあって、自分にはないものは何か。それは教養だと思い至り、時間を見つけては本を読むようになりました。でも、自己流では難しいものがあるなと。そんなときに慶應義塾大学に通信課程があると知り、文学部で学びはじめました。40歳のときです。

イギリス「MACHINTOSH」の工場で。良質なワークウェアを求め、ヨーロッパを飛び回った。
44歳でスタイリストとして独立したのは、知り合いのアナウンサーの服選びを手伝っているうちに「スタイリングを担当してほしい」と言ってもらったのがはじまりでした。慶應で学びはじめたことによる影響も大きかったと思います。会社の外でさまざまな人たちと出会い、それまで知らなかった社会課題にも目を向けるようになると、組織に依存するのではなく、「個」としての自分を確立したいという思いが生まれました。
独立にあたり、事務所は葉山に構えようと迷わず決めました。「ハリウッドランチマーケット」は葉山に保養所を持っていて、実は、それも入社の大きな理由でした。20代のころは恵比寿の寮に住んでいましたが、ひとり足繁く葉山に通い、ヨットの技術も取得。32歳で結婚してからは、妻、長男とともに二子玉川で暮らしましたが、「いつか葉山で生活したい」という思いを持ち続けていました。
独立当初はスタイリストの仕事はほとんどなく、前職時代におつきあいのあったアパレル企業から声をかけていただいて、人材育成のお手伝いをしたりしていました。少しずつスタイリストの仕事が来はじめた矢先に、東日本大震災が起き、仕事が激減。葉山を離れた時期もありましたが、口コミでクライアントが増え、2012年には再び二子玉川から葉山に通う生活が始まりました。同じころ、僕の両親の夫婦関係が破綻。家族会議の結果、母は妹と都内に住み、父は僕が引き取って葉山の事務所で暮らしてもらうことになりました。
父が立ち上げた会社を手伝えなかったことへの後悔の念がずっとあった
長い間、父と僕の関係はどこか距離のあるものでした。父はいわゆる「昭和の父」。経営者としての苦悩もあったのでしょう。子ども心に「大変なんだな。親父は」と感じていました。半面、父には文化的な側面もあって映画や小説が好き。僕にもフランス映画やイタリア映画などさまざまな作品を見せてくれました。『007』の新作映画を見ると、パンフレットを持って仕立て屋さんに行き、スーツを作るような伊達男で、僕が映画や洋服を好きになったのは少なからず父の影響があったと思います。
父は叔父と経営方針でぶつかり、52歳で会社を飛び出しました。県外で仕事をしていた長兄と次兄を呼び戻し、小さな印刷会社を始めましたが、うまくいかず、3年ですべての財産を失って上京。御茶ノ水の瀟洒なマンションの管理人の職を得て、80歳で僕が引き取るまで夫婦住み込みで働きました。父が独立した当時、僕は20歳。役者としての道を歩みはじめようとしている時でした。「紀和が手伝ってくれたら」と父がつぶやいたことがあると後に母に聞きましたが、父なりの配慮があったのでしょう。僕には何も言いませんでした。
「自分は必要とされていないんだろう」と一抹の寂しさを感じながらも、僕も当時はなるべく父に近づかないようにしていました。父の独立が「負け戦」にしか見えなかったからです。実際、僕がそこに加わっていたら、一家総崩れになっていたかもしれません。しかし、戦国時代の侍なら、「負け戦」とわかっていても父とともに戦っていたでしょう。それが自分にはできなかったという後悔の念がずっとありました。
だから、父がリタイアし、母との関係もこじれてこれからどう暮らしていくかという時、自分の出番だと思いました。アパレルの世界で基盤を築き、スタイリストの仕事も軌道に乗り、年収もそこそこ稼げるようになった。自分がここまでこられたのは、周囲のおかげでもあるけど、僕自身も頑張った。ようやく自分で自分を認められるようになって、心のゆとりも出てきたんだと思います。
葉山で父と過ごした7年間の日々が、父と自分の関係性を変えた
スタイリストの仕事は個人事業主としてやっていましたが、葉山に父を迎えたタイミングで法人化し、父には会長に就任してもらいました。葉山のゆったりとした時の流れの中で生活した影響もあったのでしょう。父がもともと持っていた頑固さや我の強さは影をひそめ、僕に対しても、ことあるごとに感謝の言葉を口にするようになりました。

2013年、会社設立を記念し、父と慶應義塾大学三田キャンパスで。
「一緒に生活をするようになって、お前のことを初めて知った。俺にはない細やかさと決断力がお前にはある」。そう言ってくれたのも印象的でした。父には経営者らしい洞察力があり、僕の持つ「人材」としての資質を理解してくれたのだと思います。大学受験に失敗し、進路に迷っていた僕に「お前は演劇の脚本を書いたりするのが好きだっただろう。演劇や映画を学んだらどうか」と勧めてくれたのは父でしたし、役者を断念した時も「お前は学歴がないから、普通の会社では苦労する。センスが勝負の業界がいいんじゃないか」とヒントをくれました。
一方で、僕が何を考え、どう生きてきたのか、僕がどういう人間なのかは知らなかったと思います。僕自身もずっと、父に理解されていないと感じていました。今思えば、父は僕の中に自分の陰を見ていたのかもしれません。両親が御茶ノ水で暮らしていたころ、僕がふたりの顔を見に行った後に、父が「紀和が来ると、新潟のにおいがする」と言っていたと母から聞いたことがあります。
父は事業に失敗し、生まれ故郷の新潟を捨てた。忸怩たる思いがあったはずです。一方、僕に新潟に対するわだかまりはなく、地元の友人とも交流を続けていました。その姿が鼻についたのでしょう。それは、父が新潟を捨てきれていなかったからこそなのかもしれません。今なら父の痛みが分かりますが、僕としては傷つきました。その父が、葉山でともに過ごした日々の中で、対等な「個」として僕を認めてくれた。それは、やはりうれしかったです。
二子玉川の自宅と葉山を行き来しながらの父との生活は、7年間続きました。2019年秋にがんが発覚して日に日に弱り、泊まり込みで介護をしましたが、暮れに葉山で亡くなりました。仕事もありましたし、僕は40歳から慶應義塾で学び続けていて、父のがんが発覚したのは、ちょうど大学院の修士論文執筆に入ったころでした。介護との両立はできないと判断し、その年の論文執筆はあきらめました。大変でしたが、この時ばかりはと父のことを優先して本当に良かったと思っています。父を見送った時、やれる限りのことはやったと感じました。すべてが浄化されたような、さっぱりとした気持ちになれました。
2019年春に卒結。父を見送った後、母と葉山の一軒家で暮らしはじめた
現在、慶應の大学院では、「主体性」の研究をしています。慶応文学部通信課程に入った時点ではアパレルメーカーに勤務していて、仕事にも役立つだろうと専門は美学美術史を選んだのですが、たまたま受講した社会学の授業がすごく面白かったんです。都市社会学を専門とする有末賢教授に師事し、お祭りの研究をして卒業論文を書きました。途中、独立をして忙しかったこともあり卒業まで9年半かかりましたが、学ぶことが楽しくなりましてね。母校愛も芽生え、総合政策学部の3年次に編入学。2018年には大学院に入りました。

慶應義塾大学総合政策学部時代。20代の若者たちとともに学んだ。
今だから言えることですが、洋服の世界でやっていけるようになってからも、相手が慶應卒と聞くと、心中穏やかではありませんでした。ほかの大学なら何も感じないのに、です。長い間、慶應義塾大学というのは僕にとって、物事を途中であきらめてしまった情けない自分を目の前に呼び起こす存在でした。だから、慶應を卒業し、コンプレックスがなくなったのは僕の人生にとって大きいですね。母も「親孝行をしてくれた」と喜んでくれました。
父との日々を通し、葉山という土地は僕にとってより身近になっていきました。大学でお祭りの研究をしていたことから、地元の盆踊り大会に実行委員として参加するようになり、地域の人たちとの関係も深まっていきました。一方、自宅のある二子玉川との関わりは薄れていったように思います。僕はもともと地域の人たちと交流するのが好きで、会社員時代は土日に近所の人たちと集まったり、地元のお祭りに参加したりして楽しく過ごしていました。でも、独立してからは土日にも仕事があり、地域にかかわる機会が自然と減っていきました。
本音を言えば、葉山で家族と暮らしたいという思いもあったんです。でも、妻は二子玉川が好き。地元で自分の世界を築き、情熱を傾けられる仕事も見つけつつありました。一緒に過ごす時間が減って、夫婦関係がぎくしゃくするようになり、息子が高校3年に進級した2019年春に卒婚。父を見送った後、2020年2月から都心の妹の家で暮らしていた母を引き取り、葉山でふたり暮らしはじめました。
ここが自分の生きる場所。葉山の地に、しっかりと根を下ろしていきたい
母には5年ほど前から時々、都心のテレビ局での仕事をアシスタントとして手伝ってもらっていたんです。母には新潟に嫁ぐ前にテレビ局で衣装づくりに携わった経験があり、手先も器用なので、助かっていました。僕と波長も合うので、父を看取った後、自然な流れで母と住むことになりました。
母と暮らすと友人たちに話すと、「自分にはできない」と驚かれることもありました。結婚していれば、自分の意思だけでは決断できないですしね。ひとり身だからできた選択かもしれません。それに、僕の場合、母がいてくれてとても助かっているんです。スタイリストの仕事は時間が不規則で外食が多かったけれど、母の手料理で健康的になり、血圧も下がりました(笑)。


この春には、裏庭で息子ともたけのこ狩りを楽しみ、母が料理の腕をふるった。
葉山の海と緑に包まれ、母も都心で暮らしていたころよりも生き生きしています。大学生になった息子も時々顔を見せてくれ、なかなかにぎやかです。40年ぶりの母との暮らしがこんなに楽しいものだと思いませんでした。母との暮らしはいずれ終わるもの。一緒にいられる今をかけがえのないものだと感じています。
母は今も週1回ほど僕の仕事を手伝ってくれています。「こき使われて、大変」とボヤいていますが、母の姿を見ていると、「誰かから必要とされている」という感覚が人を動かし、それがなくなることによって人のいろいろな機能が止まっていくのではと思います。人生100年時代、僕の人生はまだまだこれからですが、僕も価値を認められる仕事をし続け、生涯必要とされる存在でありたいですね。
その舞台が、新潟かもしれないと考えていた時期もありました。いつかは故郷に戻りたいという気持ちもあったんです。ところが、ここ数年、大学院の研究を通して新潟の町おこしをお手伝いさせていただき、それはなかなか難しいことだとわかりました。僕は新潟が大好きだし、新潟の人たちとのつながりも大事なもの。しかしながら、まだ新潟には呼ばれていないのだと実感したのです。
葉山には「平さん」と声をかけてくれる仲間がいるし、心を安らがせてくれる海や山があり、父との思い出もある。ここが自分の生きる場所だから、この地にしっかり根を下ろしていきたいと思っています。
(取材・文/泉 彩子)

ディレクションとスタイリングを担当したカレンダーの完成を記念し、テレビ朝日アナウンサー矢島悠子さんと