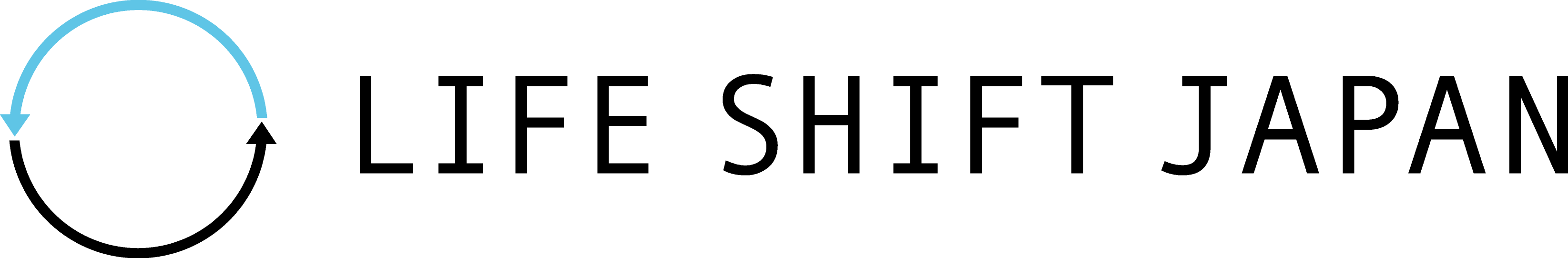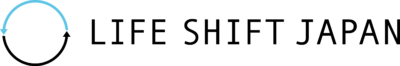30代後半にご両親を立て続けに亡くして以来、家族の思い出が詰まった神奈川県横浜市の大きな一軒家をひとりで守り続けてきた松野美穂さん。「家を守ることだけが生きがいだった」という松野さんがその家を手放して55歳で移り住んだのは、ロフト含め8畳のシェアハウスの一室でした。
松野美穂さん(NO.111/シェアハウス運営スタッフ)
■1963年、神奈川県生まれ。桑沢デザイン研究所卒業後、インテリアデザインの仕事を経てイギリスに留学。帰国後、美術館の企画に携わる。1998年にリフレクソロジスト、アロマセラピストとして活動を始める。2005年から6年間、モンテッソーリ教育のインターナショナルスクール(幼稚園)にアシスタントとして勤務。プライベートでは2001年に他界した両親の家をひとりで守り続けた。2011年の東日本大震災を機に家にこもりがちになるが、2018年、鎌倉のシェアハウスで暮らしはじめ、徐々に社会とのつながりを取り戻す。現在はシェアハウスの運営会社のスタッフとして働いている。
■座右の銘 「実るほど頭を垂れる稲穂かな」
「美穂」の名の由来で、両親によく聞かされた言葉。「意味を深く感じ、意識しはじめたのは社会人になってからです」と松野さん。
たくさんの人たちが集う、にぎやかな一軒家で育った
鎌倉駅から徒歩15分。緑に囲まれた静かな住宅地に佇む一軒家のシェアハウスで暮らして5年が経ちます。ここには20代、30代を中心に60代まで多世代の13人が住んでいて、会社員、フリーランス、学生さんなど職業もさまざま。海外で暮らした経験のある人も多く、知らない世界の話を聞けるのが楽しいです。日常の何気ない会話で、ルームメイトの視点や感覚から気づかされることも多く、多様性をすごく学べる場所だと感じています。

シェアハウスのリビング。奥にキッチン、インナーバルコニーと続く
ここで暮らすまでは、横浜の一軒家にひとりで住んでいました。私が10歳の時に社宅から移り住み、両親、姉と私と弟の5人で暮らした庭つきの家です。両親は人が大好きで、困っている人がいれば父がわり、母がわりとなって助けるような人たち。家にはいろいろな人たちが来て、数十人を呼ぶようなパーティーもよく開いていました。近所の人もしょっちゅう集まり、行き来しやすいように垣根に穴を開け、玄関も開けっ放しでした。
やがて姉と弟は結婚して独立し、海外と日本を行ったり来たり。私も28歳でイギリスに留学して家を離れましたが、帰国後は再び両親の家で暮らし、姉と弟もことあるごとにそれぞれの家族を連れて帰ってきて、にぎやかさは相変わらずでした。

イギリス留学中に訪ねてきてくれた母と。「キャリア組」ではなく専業主婦志向もない私は同世代では少数派だったが、母はそんな私を面白がってくれた。
35歳でリフレクソロジーサロンを開業した矢先、同居の母の闘病が始まった
私がイギリスから帰国したのは31歳の時。留学前はインテリアデザイナーとして働き、帰国後は美術館の企画をする仕事に就きました。楽しく働いていましたが、「手に職をつけ、長く働ける仕事を」と考えてリフレクソロジーやアロマテラピーを勉強し、35歳の時に自宅でサロンを開業。その矢先、母にがんが見つかりました。
当時、母は59歳。明るく優しい人でしたが、抗がん剤治療の過酷さから感情の波が激しくなり、うつ状態になると、父にきつく当たりました。暗い顔を人に見せなかった母が甘えられる相手は、父だけだったのだと思います。母のつらさを思うと誰かに相談することもできず、父と私だけで向き合いました。
そんな日々が数カ月続いたある日、病室で母が「お父さんは優しい人よ。私、今、お父さんに恋しているの」と言いました。母が天国に旅立ったのは、その一週間後。父は最後の最後まで母の手を握り、「頑張れ」と声をかけ続けました。すると、母が一瞬息を吹き返し、「ありがとう」と言いました。それが母の最後の言葉でした。
母が息を引き取った時、病室の外には親戚や友人が何十人も列をなし、お葬式には、雪の降る日に600名もの人たちがお別れに来てくれました。

母が亡くなる少し前に、神父様と家族と。叔母はシスターで両親もクリスチャン。私も母の他界後、洗礼を受けた。
両親が立て続けに他界。立ち直れたのは「人がいてくれたから」
母は亡くなる少し前に、こんな言葉も私に遺しました。「美穂ちゃん、ごめんね。ありがとう。あなたは私に似てつらいことを言えない人。でも、お父さんには何でも言いなさい」。
うちは離れて暮らしていても、いざとなった時の家族の団結力が強く、姉と弟も母の病気が重いと知ってわざわざ海外から引き揚げてきたほど。きょうだいも頼りになりましたが、一緒に暮らす父はやはり大きな存在でした。ところが、その父も母の他界から10カ月後にがんで亡くなりました。
何も悪いことをしていない両親がどうしてこんなに早く、と思いました。しばらくは泣いてばかりで、日常のふとした瞬間にふたりの顔が思い浮かび、嗚咽がこぼれました。人の健康を預かる仕事に就きながら、一緒に暮らしている両親を守れなかった自分が不甲斐なく、人の体に触れるのが怖くなって、リフレクソロジーサロンも開店休業状態でした。
立ち直れたのは、「人がいてくれたから」でした。母の時も父の時も、亡くなって数か月は毎日のように弔問のお客さまがいらっしゃり、ひとしきり思い出話を語り合い、みんなで泣きました。そして、父や母が「夢に出てきて、こんなことを言っていました」と口々にメッセージを残していってくれました。
サロンのお客さまも心を支えてくださって、「細く長くでも続けていければ」と出張で施術を再開した42歳の時、友人から「都内にあるモンテッソーリ教育のインターナショナルスクール(幼稚園)でアシスタントを探しているから、やってみない?」と声をかけられ、リフレクソロジーの仕事を続けながらパートタイムで働きはじめました。
東日本大震災を機に家にこもり、人とのつながりを感じられなくなった
モンテッソーリ教育は私の肌に合っていて、先生や子どもたちと笑顔で過ごせ、スクールでの仕事はとても楽しかったです。パートタイムながら待遇も良く、10時半から15時半の勤務で月給20万円。リフレクソロジーの仕事とも無理なく両立でき、いいことづくめ。おかげで自信を取り戻し、前向きに働いていた47歳の終り、東日本大震災と原発事故が起きました。
外国人が次々と国に引き揚げてインターナショナルスクールは休校に。周囲には原発事故の影響を考えて地方へ移住する人もいて、弟のお嫁さんも子どもたちを連れて沖縄で暮らしはじめ、私も彼女と一緒に行くつもりでした。でも、弟から「この家を守ってほしい」と言われてしまい、その言葉をはねのけることができませんでした。広い家にポツンとひとり残され、深い孤独を感じました。

東日本大震災が起きた後、移住を考えて弟の家族と沖縄を度々訪れていたころ。
そんな中、インターナショナルスクールを退職し、横浜でアロマテラピーのサロンを開設。自宅近くで職を探し、両輪で生計を立てていくつもりでしたが、条件に合う仕事がなかなか見つかりませんでした。ありがたいことに両親が残してくれたお金もあり、すぐに生活に困るというわけではなかったけれど、生活の基盤がぐらついている感じがあって。時間が経つにつれて金銭面の不安がひたひたと心に押し寄せ、必要以上の倹約をするようになりました。
シングルであることや、会社員ではないことの心細さもすごく感じました。例えば、地元の市が震災孤児の里親を募集していることを知り、調べてみた時のこと。パートナーがおらず、収入も安定していない私が里親になるのは難しいことがわかり、自分に社会的な信用がないことをまざまざと見せつけられたような気がしました。
さみしさや不安が心の底に澱のように溜まり、震災から数年経ったころには軽い鬱状態に。サロンはお休みがちになり、就職活動をしようにも履歴書すら書けない状態でした。それなのに、近しい人たちが心配して「大丈夫なの?」と聞いてくれると、「あ、うん。なんとか」と強がってしまうんです。内面と外面のギャップが深まり、人と会うことがつらくなっていきました。
家を守ることだけが生きがいだった私に、「旅人」が投げかけた言葉
何も言わない私を姉や弟も理解できず、きょうだいとも少しずつ疎遠に。心のよりどころは、大好きな家族と暮らした家だけでした。両親が残した財産やものを大切に守り、美しく整えて、家族の思い出を守ることがたったひとつの生きがいでした。
そんな日々を送るうちに孤独にも慣れ、出かけることもほとんどなくなっていた50代半ば、沖縄への移住を考えていたころに知り合った女性から連絡がありました。彼女は沖縄でカフェを営んでいましたが、やめて踊りの先生になり、「葉山市でワークショップをやるから、来ませんか」と声をかけてくれたんです。
思い返せば、初めて会った時、彼女は「踊りをやろうと思う」と話していました。私がこの家に留まっている間に、彼女はあの時の言葉通りに踊りを始め、先生にまでなった。その姿に心を揺さぶられ、彼女に会いに行きました。
知らない人が集まる場所に行くのはとても怖かったのですが、思い切って行ってみると優しい人たちばかり。そのコミュニティのつながりで出会ったひとりに「旅人」がいて、少し話を聞いてみると、彼は世界中を旅しながら、インドネシア・スマトラ島のコーヒー生豆を販売したり、焙煎を教えて暮らしているとのことでした。
彼がひょんなことから我が家にほんの少し立ち寄ることになり、部屋に通したところ、玄関を入ってきた時はご機嫌だった彼の顔つきが見る見るうちに変わり、いきなりこう諭されたんです。
「ここはひとりで住んじゃダメ。お金やモノなんて、いつかなくなる。モノがなくなったって、人さえいればいい」
その言葉は、私が一番刺してほしくないところをひと突きにしました。動揺のあまり、私は半泣き状態で「あなたに何がわかるの」と怒りましたが、彼は動じませんでした。
1年かけて実家じまいをし、55歳で鎌倉のシェアハウスへ
その後しばらくして「旅人」はふらりとどこかに行ってしまいましたが、旅立つ前に彼が紹介してくれたのが、横浜にある「ウェル洋光台」というシェアハウスでした。シェアハウスというと若い世代が暮らす場所というイメージがありましたが、「ウェル洋光台」では赤ちゃんから50代までさまざまな人たちが暮らしていました。
これから先の人生をシェアハウスで暮らすという選択肢があると知り、最初は自分の家でシェアハウスをやろうと考えたのですが、構造や立地などの問題で難しく、一度はあきらめました。でも、人に囲まれ、にぎやかな家庭で育った私には、人とのつながりを感じられない生活はもう限界だったのだと思います。「人さえいればいい」という「旅人」の言葉がいつまで経っても心から消えず、両親が亡くなって以来守り続けてきた家を手放すことを決意。1年かけて家じまいをし、2018年7月に現在住む鎌倉のシェアハウスに移り住みました。
家を売りたいと最初に話した時、弟は「家は残したまま、好きな場所に住めばいいじゃない」と提案してくれました。でも、それはできませんでした。実際に一時期都内で暮らしたこともあったけれど、半年でも空き家になると、家って朽ちていくんです。あの家は、私にとって家族の思い出そのもの。その家が自分のせいで朽ちていくのを見るのは耐えられない、と思いました。家が存在する限り、私は家を離れられない。離れるには、家を手放すしかなかったんです。
私にパートナーや子どもがいたり、揺るぎないキャリアがあって、どっしりと構えることができれば、あの家で暮らし続けられたかもしれません。「私に社会的な力があれば家を守れたのに」と両親に申し訳なくて、家の売却を決意してからの日々は、部屋を整理し、思い出を片づけてながら「ごめんね、ごめんね」と何度も泣きました。
そんな私を見かねたのでしょう。父が夢に出てきて、「まだ家を売ってなかったの? とっくに売ったと思っていたのに」と(笑)。姉や弟にはなかなか理解してもらえませんでしたが、後に父の夢の話をしたら、「いい言葉だ」と言っていました。大人になった姪たちは何かと私を気遣い、片づけの手伝いにも来てくれました。

引越しの荷物を運び出し、何も無くなった実家での最後の写真。この後、シェアハウスへ。
シェアハウス暮らしを満喫できるのは「孤独を愛せる大人」
鎌倉のシェアハウスで暮らそうと決めたのは直感のようなものでしたが、引っ越してすぐにその直感が間違っていなかったとわかりました。両親が他界し、ひとりで暮らすようになってからはずっと眠りが浅かったのに、ここでは最初の夜から熟睡できたんです。
1週間経ったころには、家族でにぎやかに暮らしていたころの自分を取り戻し、人とも楽しく話せるし、体も軽く感じて。もう、本当に楽になったんです。こんなことなら、もっと早くシェアハウスに移り住めばよかった、と思いました。

シェアハウスで暮らしはじめたころ。共同のリビングで飲み会の様子。
鎌倉で暮らして5年。最初の数年は以前から関心のあった介護の仕事をやり、今はこのシェアハウスの運営会社のスタッフとして働いています。私はインテリアの仕事をしていましたし、家を守り、きれいに保つことが生きがいでしたから、お部屋を整えることはお手のもの(笑)。そこを見込んでスカウトしていただいたのかなと思っています。
シェアハウスでは価値観も考え方も違う人たちがひとつ屋根の下で暮らしますから、人間模様もいろいろ。トラブルに巻き込まれ、途方に暮れたこともありました。でも、助けてくれた人たちがいたし、「人は本当にそれぞれ違うんだ」ということを理屈抜きで学ぶことができました。
ここはキッチンも洗面台も共用で、ありのままで暮らす場所なんですよ。みんな、起きたてで髪がハネたまま歯磨きをしていたり、眉毛なしの顔でパンをかじっていたりする。「ちょっと元気がないな」「機嫌が悪いのかな」というのも、一緒に暮らしていれば何となくわかります。
長い間、誰かとそんな姿を見せ合うことはありませんでしたから、最初は私もおそるおそるでした。でも、自分が意識しなければ、相手も意識しない。相手は見ていないんです。他人同士がこんなにおたがいを知ることのできる場はないと思いますね。
人が見せ合うのはきれいな面ばかりではないけれど、だからこそ人間は面白いし、人と暮らすのは楽しい。「旅人」の「人さえいればいい」という言葉は本当にその通りでした。一方で、「自分は自分」という感覚がないと、暮らしていけない場所だなとも感じています。そういう意味では、孤独を愛せる大人こそシェアハウスの暮らしを満喫できるかもしれません。
価値観は十人十色だから、還暦世代の暮らし方も人それぞれでいい
シェアハウスは住人の入れ替わりも頻繁にあり、この5年間で一緒に暮らした人たちは30人以上。卒業生のネットワークが全国に広がっていて、各地に友人がいます。今年5月には、卒業したシェア家族も集まって私の還暦を祝ってくれました。5年間の映像を編集した動画を見せてもらい、「あったね。こんなこと」と大笑い。赤いワンピース姿の私を囲んで「美穂さん、おめでとう」と言ってくれる白い服のみんなが、天使に見えました。

還暦のお祝いをしてくれた新旧のシェアハウスメンバーと。ここで知り合って結婚したメンバーもいて、結婚式にも出席させてもらった。
還暦までをひとつの人生とするなら、人生一巡。つらいこともあったけれど、家族や友人に支えられ、ラストスパートの5年はたくさんのシェア家族もできて、一度目の人生は見事な幕引きができました。人生、何があるかわかりませんね。60歳までの日々を思い返すと、大好きなウッディ・アレンのコメディを見ている時のような気持ちです。
シェアハウスで暮らすことを周りに話した時、身を乗り出して聞いてくれる人はあまりいませんでした。それが私くらいの年齢の人たちの一般的な感覚かもしれません。「これからシェアハウスに住むなんて、みじめじゃない?」と言う人もいました。一方で、ご主人を亡くしてひとりで暮らし、老人ホームへの入居も考えているという80代の方からは「いいアイデアね。あなた賢いわ」とおほめの言葉もいただいたりして(笑)。
価値観は十人十色だし、時代や状況によって変わりますから、還暦世代の暮らし方も人それぞれでいい。ただ、「選択肢はいっぱいある」ということを知ると、人生が楽しくなりますよね。シェアハウスもその選択肢のひとつだし、もしかしたら、これからもっと新しい暮らし方が生まれるかもしれません。
私も、これからずっとシェアハウスで暮らし続けるかどうかはわかりません。ここは気に入っているけれど、家やコミュニティを自分の手で作れたらという夢もあるんです。人生は死ぬまで未知。だから、最後まで思いっ切り冒険を楽しみたいと思っています。
(取材・文/泉 彩子)
*ライフシフト・ジャパンは、数多くのライフシフターのインタビューを通じて紡ぎだした「ライフシフトの法則」をフレームワークとして、一人ひとりが「100年ライフ」をポジティブに捉え、自分らしさを生かし、ワクワク楽しく生きていくためのワークショップ「LIFE SHIFT JOURNEY」(ライフシフト・ジャーニー)を提供しています。詳細はこちらをご覧ください。