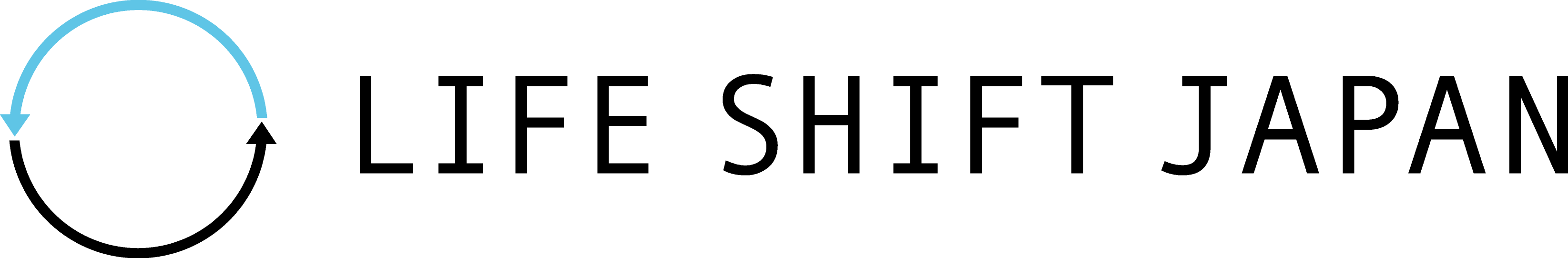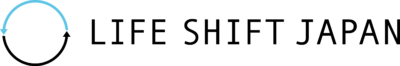村井満さん(No.100)/株式会社ONGAESHI Holdings 代表取締役CEO
■1959年生まれ、埼玉県出身。早稲田大学法学部卒。1983年日本リクルートセンター(現リクルートホールディングス)に入社し、人事担当の執行役員、香港の関連会社取締役社長などを歴任。2008年から2013年までJリーグ理事。2014年1月にチェアマンに就任。リーグの財政基盤を立て直し、新型コロナウイルス対策にも手腕を発揮。4期8年の任期を全うし、2022年3月に退任。 2022年4月、株式会社ONGAESHI Holdingsを設立し、代表取締役CEOに就任。6月にはぴあ株式会社や株式会社WOWOWの社外役員に就任。スポーツやエンターテインメント産業の活性化にも取り組む。
■家族:妻、長女、次男、孫4人(5歳、1歳、3歳、0歳)
■座右の銘:なし
30年勤務していたリクルートから、Jリーグチェアマンに
30年間リクルートに勤務していた私がJリーグに関わるようになったのは、人材紹介会社リクルートエージェント(現リクルートキャリア)の社長時代にCSRの一環としてスポーツ選手のセカンドキャリア支援をしたことがきっかけ。そのご縁で2008年からJリーグの社外理事を務め、2014年1月に第5代チェアマンに就任しました。
当時のJリーグは人気低迷で入場者数が減り、長年支えてくれていたスポンサーも離脱。財政再建と組織改革が大きなテーマとなっていたことから、ビジネス経験があり、生え抜きとは異なる視点を持つ人間にやらせてみようということで私に白羽の矢が立ったのだと思います。しかし、私は大のサッカー好きではあるものの、サッカーを生業にしたことはない「門外漢」。Jリーグのチェアマンとして前代未聞の経歴です。おまけに直近の3年間はリクルートの香港法人の代表として現地に赴任しており、Jリーグの試合はほとんど観ていませんでした。
そんな私にできることは、足で稼ぐことくらいしかありません。Jリーグのチェアマンになって最初にやったのは、J1からJ3まで全国36都道府県51クラブ(当時)すべてを回ることでした。クラブハウスやスタジアムを訪れるのはもちろん、クラブを応援してくださる自治体や地元企業の方々にもお会いし、夜はサポーターが集まる居酒屋にも行きました。
ありとあらゆる場で相手の話を聞き、わからないことは教えてもらう。そして、自分が気づいたことは言う。そんな日々を通して実感したのは、Jリーグのクラブにはそれぞれのカラーがあり、抱える課題やJリーグへの要望も多種多様だということ。各クラブの共通点を見つけ、改革を進めるための突破口にしたいと考えていましたが、なかなか見つからず、天を仰ぎました。
ところが、半年ほどの全国行脚を終えた時、51クラブ全てに賛同を得られたアジェンダがひとつだけありました。「デジタル化」です。当時のJクラブはデジタル化にそれぞれが投資をしていましたが、高いITスキルを持った人材がいるわけではなく、発展途上の状態でした。そこでJリーグがデジタルプラットフォームを構築し、各クラブで活用するだけでなく、クラブ間で情報共有もできるようにしたんです。
結果、Jリーグのデジタル環境は飛躍的に上がり、8年間の在任中に実施した改革の要となったデジタル事業の足がかりになりました。2016年に結んだ英国発のスポーツ専用動画配信サービス「DAZN(ダゾーン)」との10年間で2100億円の放映権契約も、この取り組みが実施されていなければ成し得なかったはずです。
20代後半までは、隙あらば逃げようとしていた
振り返れば、Jリーグのチェアマンとして進むべき方向性を私に示してくれたのは、さまざまな人たちと胸襟を開いて対話したあの全国行脚でした。そして、先が見えない中、一歩を踏み出し、体当たりで人と関わっていく人間に私を育てたのは、リクルートでの30年間です。
かつての私は、困難に直面した時に逃げようとしがちでした。幼少期は友だちと野山を走り回り、「山猿」のように本能のままに自分を出していましたが、思春期に入ったころから人と関わることに苦手意識を持つようになりました。高校時代は公立男子校でサッカーに打ち込み、大学時代はスキーやテニスのサークルに入って華やかな学生生活を送る学生たちを横目に、学生服を着て一升瓶を抱えて酒を飲むようなアナクロなサークルに所属。今思えば、自信のなさの裏返しだったのでしょう。人が行く方向とは逆へ、逆へと行くような意固地さがありました。

大学3年生の時に早稲田大学精神高揚会の仲間と中国横断600キロの旅へ。地元の銭湯にて
リクルートに入社を決めたのも、ほかにはないことをやろうとする社風に何となく自分と共通するものを感じたからです。ところが、入ってすぐに「自分が来るところではなかった」と思いました。こじんまりした会社だと思い込んでいたのに、同期入社は150人もいて、優秀で個性的な人がごろごろいる。職場には女性社員も多く、華やかな雰囲気で、気後れしてしまったわけです。
心の奥底ではその輪に入りたいと思っているけれど、入れない。自分の居場所がないから、遅い時間まで会社に戻らず飛び込み営業を続け、さらに孤独感を強めるという悪循環でした。大勢の前で話すのが苦手で、朝礼で話をしなければいけない日に「直行があります」と言って朝礼を休んだこともあります。営業成績も目立たず、新人時代は劣等感のかたまりでした。
20代は事あるごとに「辞めたい」と思っていましたね。仕事で大失敗をして思い詰め、上司に辞表を出し、妻と2歳の長男を連れてアメリカへ旅立ったこともあります。28歳の時です。頭を冷やして2週間で帰国。出社したところ、辞表はまだ上司の机の中にありました。失敗も挽回できて事なきを得ましたが、このころまでは、隙あらば逃げようとしていました。
失った息子の表情を思い出し、逃げている自分に自己嫌悪を感じた
アメリカ旅行の直後、私にとって人生で最も大きなできごとが起きました。長男が2歳で亡くなったのです。心臓突然死でした。亡くなった直後は呆然とし、しばらくは現実を受け止められない精神状態が続きました。妻はもっとつらかったはずです。
最初は長男との日々を思い返すことすらできませんでした。でも、時間によって少しずつ自分の中の何かが癒され、長男のことを思い浮かべた時、お腹が空いたらぎゃあぎゃあ泣いたり、楽しいとケタケタ笑ったり、心のままの表情をすごくきれいだと感じたんです。飾らず、まっすぐに自分を表現する長男の姿は、あんなに幼くても人を引きつけたなあ、と。
一方、私はと言えば、お客さんの前で愛想笑いをしながら「天気がいいですね」なんて言いたくもない社交辞令を言っていたりする。そう考えた時、「自分は一体、何をしているんだろう」と思いました。
と言うのも、私には長男の死によって気づかされたことがありました。自分には何も所有できないし、コントロールできないということです。お客さんは思い通りにならないし、職場の仲間ともうまくつき合えない。自分の子どもくらいは自分のものだと思っていたら、自分の子どもさえ自分の許可なく死んでしまうということが起きました。
我が子すら所有できない、コントロールできない。裏を返せば、それは「守るべきものなど何もない」ということです。それなのに、自分はまだ何かを守ろうと逃げている。自己嫌悪を感じました。同時に、これからは私も修行をして長男のあのきれいな表情に近づきたい、と思ったんです。
それで私が何を始めたかというと、サッカー観戦です(笑)。サッカーは点数が入りにくい競技なので、選手が1点を入れると観客が感情を爆発させますよね。大の大人が泣いたり、叫んだりして喜怒哀楽を発露する。その姿のきれいさに引かれ、スタジアムに通い詰めました。当時は日本代表の試合も、地元・浦和レッズの試合もほぼ全試合観ていました。

1997年11月16日、日本代表がFIFAワールドカップ初出場を決めたマレーシアのジョホールパルにて
「修羅場」だった、リクルート事件からの日々
そのころに起きたのが、「戦後最大の疑獄事件」と言われたリクルート事件(1988年)です。
事件が起きて会社は大きく揺れ、社会的信用も地に落ちました。事件だけでも会社が潰れそうなのに、バブル崩壊で日本経済が低迷し、1994年には1兆4000億円の有利子負債が発覚。それでも商品やサービスに将来性があれば、希望が持てます。ところが、当時はインターネットが急速に普及しはじめた時期。「紙媒体は10年でなくなる」と言われ、実際、リクルートの看板商品だった「リクルートブック(新卒採用者向けの企業情報誌)」は2005年になくなります。
世の中から叩かれ、お金もなく、本業さえどうなるかわからない。私がリクルートの人事部長や人事担当の執行役員を務めたのはそんな10年間でした。辞めようとする社員を引き留めるのは日常茶飯事。新卒社員を3名しか採用できないという人事の責任者として屈辱的なことも経験しました。私自身が辞めたとしても、誰も不思議に思わなかったでしょう。
辞めなかったのは、「辞める隙がなかった」というのが偽らざるところです。会社が明日どうなるかわからないわけですから、体よくやってうまくいく仕事は何ひとつありません。社内・社外にかかわらず、相手と本音をぶつけ合い、全身全霊で目の前の課題に向き合う日々でした。
まさに修羅場でしたが、振り返れば、居心地がよかった気すらします。否応無く自分をさらけ出すしかない環境は、長男を失ってもなお何かを守ろうとする自分に「一体、何を守ろうとしているのか」と問い続けていた、当時の私の心根に合っていたからです。

本社の人事部門に異動して間もないころ。営業の仕事が好きだったので、当初は不本意だと感じた
「信頼関係に理屈はない」と体に刻み込まれた日
最終的にリクルートは1兆4000億円もの借金を約10年で返済しました。会社の危機を仲間と乗り越えた経験が、自分を鍛えてくれたことは間違いありません。しかし、人間が本来持つ性質というのはなかなか変わらないものです。
役員にまでなっても私は相変わらず「ビビリ」で、人前で話すとなると前の晩は眠れませんでした。45歳でリクルートエージェントの社長に就任した時にも、約600人の社員の前でスピーチをしなければならず、怖気づきました。それでも逃げるわけにいきませんから、自宅で猫を抱いて自己紹介の練習をし、猫にひっかかれたりもしました。
そんな私に変化を与えたのは、40代後半からリクルートの海外進出に関わり、アジアで仕事をした経験です。私の英語力は中学生レベルで、もちろん海外赴任の経験はありませんでした。今でも忘れられないのは、香港に本社を置くアジア最大規模の人材紹介会社を買収した時のことです。
従業員700名ほどの会社で、社長はハーバードのビジネススクールを卒業後、モルガン・スタンレーに就職し、米国のエグゼクティブ・サーチを経て母国で起業したルイーザという女性でした。買収の交渉が始まったのは2010年ですが、その会社とは数年前に連携を探った時期があり、ルイーザとは何度も酒を酌み交わし、アジアでの人材ビジネスについて夢を語り合った仲でした。
久しぶりに会った私が買収の話を切り出すと、ルイーザは用意した資料を見ようともせず、こう言いました。「双方にメリットのある話だと思う。ただし、会社を売却するというのは、大事に育てた会社と社員たちをあなたと結婚させるようなもの。あなたが社員を説得できたら、この話を受ける」。
断る選択肢はありません。ルイーザが上海に幹部50名ほどを集めて会議が開かれ、私がプレゼンテーションをしました。ところが、英語がつたないだけならまだしも、緊張で足が震え、内容もボロボロ。幹部の反応は、それはもう冷ややかなものでした。
何とかしなければと思い、ルイーザに頼み込んで、少し離れた場所にあるレストランをディナーの会場として予約。送迎のための観光バスも借りてもらいました。そして、バスの中で歌ったり、片言の英語で思いのたけを語ったんです。すると、幹部の皆さんが心を開いてくれ、帰りのバスではみんなで合唱(笑)。最終的に買収が成立しました。
香港駐在中の3年間で私は4社の買収に関わり、アジア26都市に拠点を広げました。その原点は、初めて会った外国の人たちと肩を組みながら歌ったあの日です。言語や文化が異なる相手でも、体当たりで自分をさらけ出せば、わかり合える。信頼関係に理屈はない、と体に刻み込まれました。あの日がなかったら、Jリーグのチェアマンも絶対に務まらなかったと思います。

ルイーザが創業した会社の社員との懇親会。香港映画の主題歌「上海灘」を仮装して歌った
岐路に立った時は、「緊張すること」を選び続けてきた
Jリーグのチェアマンの就任会見で、私は「命を賭して、人生を賭けてやります」と言いました。大げさに聞こえるかもしれませんが、すでにお話ししたように当時のJリーグは財政難で存亡の危機にありました。加えて、翌年からの実施がすでに決まっていた「2ステージ制」がサポーターから大ブーイングを受けているという逆風での船出でしたから、死ぬことまではないにしても、命を削ることにはなると思っていました。

2014年1月31日。第5代Jリーグチェアマンに就任した時の会見の様子
それほどのリスクもある話をお受けした理由は、「迷った時は、緊張することを選ぶ」と決めていたからです。リクルートでの30年間で私は何度も「緊張すること」に出合い、経験則をふたつ得ました。ひとつは、「緊張すること」から逃げずに体当たりすることによって、価値のあるものを得るということ。リクルート事件然り、アジア事業然りでした。
もうひとつの経験則は、自分が緊張するのは大切なものが目の前に現れ、それが手に入るか、入らないかギリギリの時だけだということです。簡単に乗り越えられることなら緊張しないし、どう頑張っても自分には絶対にできないことには緊張しません。
チェアマン就任の打診をいただいた時、最初は「自分にできるわけがない」と思い、半分冗談と受け止めて笑っていましたが、相手が本気だとわかったとたん、身震いするような緊張感が襲ってきました。だから、後先も顧みず、その場で「やります」とお返事しました。条件反射のようなものです(笑)。
チェアマン就任後も、岐路に立った時は、「緊張すること」を選び続けてきました。2022年3月にチェアマンを退任後、「ONGAESHI ホールディングス」を設立したのもそうです。基盤として投資ファンドを設立しましたが、やりたいのは門外漢の私と夢を追いかけてくれたサッカー界、スポーツ界、地方企業への「恩返し」です。
具体的には、Jリーグクラブの経営人材の育成事業に少しずつ着手しています。実現したいのは、サッカー選手の中から日本をリードする経営者を輩出すること。アスリート出身の優秀な経営人材が地方企業と結びつけば地域活性化につながりますし、アスリートのセカンドキャリア支援にもなります。夢をあきらめずに物事に体当たりで取り組んできた人が報われる環境を整えたい。ひいてはそれがスポーツ振興につながる、とビジョンを描いています。
Jリーグのチェアマンを経験し、さまざまな現実を目の当たりにしたから言いますが、このビジョンを実現するのは簡単ではありません。ビジョンというより「野望」に近いです(笑)。前例がなく、何もかもが手探り。緊張どころか、行き場のない悶絶の日々です。だからこそやろう、と思っています。
辞めた仕事のことは意図的にスイッチを切り、「真空」になる
「緊張すること」をいくつも乗り越えてきた今も、逃げようとする自分はうっすらとでも存在していて、消えたわけではありません。「お前は逃げるのか」「いや、もしかしたら、逃げないんじゃないか」というような自問自答は常にあります。
だけど、逃げたら、それに誰ひとり気づかなくても、ほかならぬ自分にはわかるんですよ。「お前、あの時逃げたな」って。逃げた時の自己嫌悪は澱のように蓄積されていきます。結局、私のこれまでの人生はその蓄積に向き合って「逃げるか」「逃げないか」と自問自答し、「逃げまい」と格闘することによって過去の自己嫌悪の一つひとつを決着していくプロセスだったように思います。
プライベートも仕事も、綿密な計画をして動くタイプではないですね。キャリア形成についてお話すれば、「偶発的なもの」というのが私の根本的な考えです。学術的な理論でも言われていますが、私自身がまさにそうでしたから。リクルートを退職する時、先のことは何も決めていませんでした。当時あったのは、「緊張する方を選ぶ」という基準と「大の大人が泣いたり、笑ったりしているサッカーって素敵だな」という好奇心だけ。そこに思いがけず、Jリーグのチェアマンのお話が来ました。
もうひとつ、私の場合、辞めた仕事のことは意図的にスイッチを切り、以前の職場にも足を踏み入れません。リクルートを辞めた時点では「老害になりたくない」という思いからそうしたまでなのですが、数年前にある人にその話をした時、「一度すべてを捨てて真空状態になったからこそ、Jリーグのチェアマンになった時に、新しいものをものすごい力で吸い込めたのでは」と言われ、「なるほど」と思いました。会社を設立したとはいえ、今はまだ「真空」みたいなもの。サッカー関連のニュースはなるべく見ず、時間を見つけてキャンピングカーで旅をしたり、興味のあるボランティアにふらりと参加したりしています。
最近はよく、孫が遊びに来ましてね。亡くなった長男と同じ年ごろなのですが、やっぱり泣いたり、笑ったり、混じり気のない表情がきれいで引きつけられます。
「自分をさらけ出す」ということについては、朝礼で話すことすら逃げていた私がJリーグのチェアマン時代には「むしろ“天日干し”になろう」と舵取りを変えていました。Jリーグのチェアマンというのは何か隠そうとした瞬間にインターネットの記事にされてしまう稼業。さらけ出すことを拒否したって無理なんです。
それならば、と徹底的に自分をさらけ出し、おかげで退任時には「自分にできることは、逃げずにやり切った」という思いがありました。だけど、まだまだですね。私の笑顔なんて、やっぱり汚れた作り笑顔です。修行しても、修行しても、あの笑顔にはなれません。
それでもあの表情に少しでも近づきたい、と思い続けています。長男は学校に通うこともなく、恋愛も知らずに生涯を閉じました。あの短い命がどれだけ私に影響を与えているかわかりません。私も彼のように命を燃やし尽くして生きたいと思っています。
(取材・文/泉 彩子)
*ライフシフト・ジャパンは、数多くのライフシフターのインタビューを通じて紡ぎだした「ライフシフトの法則」をフレームワークとして、一人ひとりが「100年ライフ」をポジティブに捉え、自分らしさを生かし、ワクワク楽しく生きていくためのワークショップ「LIFE SHIFT JOURNEY」(ライフシフト・ジャーニー)を提供しています。詳細はこちらをご覧ください。