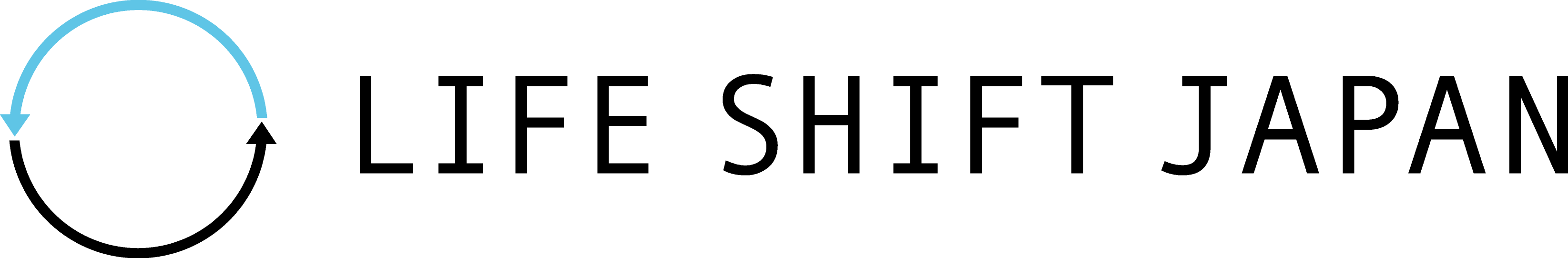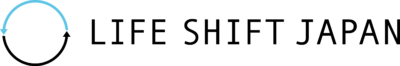坪内知佳さん(No.102/株式会社GHIBLI代表取締役)
■1986年、福井県生まれ。名古屋外国語大学を中退後、山口県萩市へ移住。2010年10月に漁業の世界に飛び込み、2011年11月、3船団・約60名の漁業者とともに任意会社「萩大島船団丸」(個人事業)を設立し、代表に就任。 2014年に株式会社GHIBLIとして法人化し、翌年から事業の全国展開を開始。2016年にはForbes誌がアジア地域の各分野で活躍する30 歳未満の人材を選出する「30 UNDER 30 Asia」に選ばれた。2022年10月5日(水)より放送の日本テレビ系列ドラマ「ファーストペンギン!」主人公のモデルでもある。
■家族:長男、次男
■座右の銘:至誠通天
孟子の言葉で、「誠の心を尽くして行動すれば、いつかは誰かに必ず伝わる」という意味。かかつては「継続は力なり」が座右の銘だったが、最近はこの言葉の方がしっくりとくる。
仕事のために人が苦しまなければいけないのはおかしい
山口県萩市の沖合にある大島(通称・萩大島)で暮らす漁師たちとともに2010年に「萩大島船団丸」を立ち上げ、消費者に鮮魚を直接販売する事業をしています。漁師が獲ってきた魚を自ら選んで梱包し、発送までを行う直販事業は全国でも珍しい取り組みです。

獲れた魚は船上で血抜きし、すぐに箱詰めして出荷。市場を通すより数日早く消費者に届く
自己紹介をすると「萩出身なんですか?」、「ご実家がお魚屋さん?」とよく言われますが、
生まれ育ったのは福井県です。実家は実業家の家系で、祖父は40代で亡くなりましたが、祖母や一族が事業を継ぎ、父も保険業やレンタル業を営んでいました。
世間的に見れば恵まれた家庭に生まれたと思います。でも、私自身は自分の環境に対し、違和感を抱えながら育ちました。生まれつき体が弱く、友人たちとどこか距離を感じていたこともあって、周囲から「知佳ちゃんちはいいね」と言われることがイヤでした。また、私はバブル崩壊の数年前に生まれ、「失われた20年」と呼ばれた時期に子どもから大人になった世代。事業が当たり前の家に育ったこともあって、バブル期に成功し、華やかな生活をしていた人たちが経済の波に飲み込まれていく姿を目の当たりにしました。
「◯◯さんが事業に失敗して海に飛び込んだんだって」などと大人たちがひそひそと話すのを耳にしたことも、一度や二度ではありません。そのたびに「仕事のために人がそこまで苦しまなければいけないのはおかしい」と子ども心にやり場のない憤りを感じました。
人は生きるために働くのか。働くために生きるのか。当時の私には、周りの大人たちが働くために生きているようにしか見えませんでした。虚しさを感じ、ここで生きることに光を感じられない。そんなところのある子どもが私でした。

7歳の七五三で父と。父は車が好きで週末には遠くまで家族を連れて行ってくれたが、仕事が忙しく、平日はほとんど顔を合わせなかった
CAを目指してひたすら努力を重ねた学生時代
「福井を離れ、違う世界へ飛び出したい」という思いから、最初に憧れた職業は船乗りやパイロット。海を超え、空を超えて世界を飛び回る姿が自由でまぶしく見えました。ところが、母に話すと、「船乗りもパイロットも、普通、女の子はなれないわよ」とキッパリ言われました。
「“ 普通”って何だろう?」と引っかかりはありましたが、母の言葉を受け入れ、「それならば」と女性でもなれるキャビンアテンダント(CA)を志したのは、小学校2年生のころ。それからは、夢に向かって突き進みました。
小中高と猛勉強をし、高校では交換留学プログラムに合格してオーストラリアに1年間留学。大学は名古屋外国語大学英米語学科に進みました。みんなが2年かける単位数を1年で取るつもりで履修して、大学1年の前期はすべての科目の成績がAプラス。志望する航空会社が夏休みに開催する、「参加すれば就職も確実」と言われていたインターンにも合格し、CAになる未来しか思い描いていませんでした。
ところが、待ちに待ったインターンを目前に突然高熱が出て、倒れました。意識を取り戻した後もリンパが腫れ、40度を超える高熱が1週間以上。息をするのもしんどい状態が続き、大学1年の9月から12月まで4カ月間を寝たきりで過ごしました。大きな病院をいくつか訪ねても原因がわからなかったのですが、発症から数カ月経ったころ、ある病院で「悪性リンパ腫の疑いがあり、余命半年かもしれない」と告げられました。
再検査の結果、悪性リンパ腫ではなく特殊なウイルスによる感染症と判明し、余命宣告は取り消されましたが、大学に通えるようになってからも熱を出してはすぐ寝込む日々。CAの夢はあきらめざるを得ませんでした。今思えば、新型コロナウイルス感染症の後遺症のような状態だったのでしょう。倦怠感や体の痛みが完全に消えたのは、実はここ5年のことです。
CAになれないのなら、大学に通い続ける意味はあるのだろうか。そう考えていたころ、父の会社が倒産。その報せに突き動かされるように、大学を中退して以前から付き合っていた彼と結婚することを決めました。両親は「せめて大学を卒業してから」と反対しましたし、両親の言う通りにするのが「普通」だったかもしれません。でも、もう「普通」という言葉で立ち止まる私ではありませんでした。後に取り消されたとはいえ余命宣告を受け、人生の残りの時間を痛いほど意識したことによって、「これからは自分の感覚に素直に生きよう」という思いが私の中に生まれていたからです。

少し体調が落ち着いた大学2年生の冬、CA以外の新たな道が見つかるかもしれないとカナダに短期留学したが、現地で寝込み、予定を切り上げて帰国した
アジとサバの区別もつかなかった私と、漁業の出合い
彼の勤務地だった萩で専業主婦として暮らしはじめ、間もなく子どもも授かりました。ところが、結婚生活はうまくいかず、息子が1歳半の時に別居。萩市の外れに家賃2万3000円のアパートを借り、翻訳や企画などの仕事を個人事業主として細々と始めました。
漁業に関わるようになったのは、翻訳の仕事のクライアントだった観光協会の依頼で旅館のコンサルティングを請け負い、年末の繁忙期に2日間忘年会のお手伝いをした時に、萩大島の巻き網船団の漁猟長だった長岡(現「萩大島船団丸」船団・長岡秀洋さん)に出会ったことがきっかけです。
たまたま両日とも長岡と顔を合わせたことから会話を交わし、「萩で翻訳やパソコンを使った仕事をしているので、何かあったら声をかけてください」と名刺を渡したところ、長岡は漁師仲間にも私を紹介してくれ、ちょこちょこと事務仕事を頼まれました。2009年の暮れのことです。
最初はそれだけだったのですが、年明けのある朝、長岡から呼び出され、長岡を含め3人の漁師から「魚が獲れなくなってきたから、わしらも漁だけではなく何かをやらなければと思うけれど、どうしていいかわからない。あんたはものを考えるのが得意だし、パソコンもできる。島の未来を守るために、手伝ってくれんか」と相談を持ちかけられました。
手伝うも何も、私は漁業について何も知らない「ド素人」。アジとサバの区別すらつきませんでした。おまけに、漁師たちの生活がかかった話です。普通に考えれば、断るのが筋でしょう。私も最初は戸惑いました。でも、彼らの話を聞くうちになんだか面白いことが起きそうな気がして、つい身を乗り出して「で、何をやればいいですか?」と言ってしまいました。

萩近海の漁獲高は1984年の25万トンをピークに、私が長岡と出会った当時は3万トンまで減少。経費の高騰や後継者不足など課題が山積みで、萩大島の漁業は瀕死の状態だった
地元の漁師60名を束ね、24歳で「萩大島船団丸」の代表に
苦境を脱するために私たちが目指したのは、漁業の6次産業化(農林漁業者が生産=1次産業だけでなく、加工=2次産業、流通・販売=3次産業にも取り組むことによって産業を活性化させること)。漁師が獲った魚を自分たちで加工し、自分たちで売る仕組みを開拓することです。
長岡たちから呼び出された日から間もなく、農林水産省が「六次産業化・地産地消法」に基づく認定事業者を募集することがわかり、彼らから私が最初に依頼されたのは、その申請のための事業計画書を外部のコンサルタントとして作成すること。この時点ではまさか自分が萩大島の3つの巻き網船団からなる「萩大島船団丸」の代表として島の漁師たち60名を率いる役割を担うとは思ってもみませんでした。
「萩大島船団丸」はもともと農林水産省に提出する事業計画書に事業主体名が必要だったことから2010年10月に便宜上作った団体で、当初、代表は長岡でした。ところが、長岡が「あんたが計画書を作ったんやし、わしらにはようわからん」と言い出し、紆余曲折の末に私が就任することになったんです。当時私は24歳でした。
事業計画書は約1年かけて萩大島や萩の浜をリサーチして何度も書き直し、2011年3月14日に提出。中国・四国地方で第一号の事業者に認定されて大喜びで酒盛りをし、漁師たちから「あんたのおかげじゃ」と何度もお礼を言われました。

「萩大島船団丸」の漁師たち。左から4番目が私と漁業の出合いをもたらしてくれた長岡だ
事業の赤字を個人的に補填し、自己破産寸前だった時期も
私たちが最初に取り組んだのは、獲れたての魚を漁師が自分たちで活け締めして梱包した「鮮魚ボックス」を自家出荷すること。水揚げされた魚は「生産者→市場(漁業協同組合)→仲卸業者→小売店」という経路で消費者に届くのが水産業の商慣習ですから、漁協や関係業者にとっては面白いはずがありません。そこで、市場でメインで取り引きされる魚以外に網にかかり、たたき売り状態で売られていた魚を商品として用いることにしたのですが、激しい反発を招きました。
漁協や関係業者に一定の手数料を払うことでこの問題は何とか解決し、2011年7月に直販事業を始めましたが、修羅場はそこからでした。最初は飲食店のみを対象に販売していたのですが、顧客の開拓はゼロから。息子を保育園に預けて関西に出張を重ね、飲食店を訪ね歩いて一軒ずつ取引先を増やしていきました。ところが、ようやくご注文をいただいても魚の詰め方が悪くて商品が傷み、クレームの嵐。現在は営業も漁師たちが担当していますが、最初はビジネスマナーも何もあったものではなく、一時は顧客が半分に減りました。
「萩大島船団丸」を立ち上げて数年は仕事ばかり増えて収益は上がらない状態。当時、代表としてのお給料は月5万ほどでしたから、翻訳など以前からやっていた仕事も続けていました。今だから言えますが、事業の赤字を個人的に補填していたため、その額が膨らんで私自身が破産寸前のころもありました。2014年に「萩大島船団丸」を株式会社GHIBLIとして法人化し、銀行の融資も受けられるようになりましたが、単年での黒字化を達成したのは2017年のことです。
漁師たちとは何度も意見がぶつかり合い、とくに長岡とは取っ組み合いのけんかをしました。半年間ほど断絶状態だった時期もあります。今でも口げんかはしょっちゅうです(笑)。でも、「萩大島の未来を守りたい」という同じ目的に向けて、一緒に歩み続けてきました。「よく続けましたね」と皆さんから言われますが、何の不思議もありません。誰に強いられることなく、自分の意思でやってきたからです。

営業で港に行かない日が続き、「遊んでいる」と誤解した長岡から「出ていけ」と言われたことも。数日彼らの前から姿を消したが、その間に事業のリサーチのために秋田へ出かけた
萩大島の漁師たちと出会ったころの私は、シングルマザーになり、生活を立て直そうと悪戦苦闘しつつも、結婚生活に終止符を打ったことに後悔はしていませんでした。むしろ、「息子とここで暮らしていけたら、あとは何もいらない。これからは何でもできる」と自由を感じたのを覚えています。一方で、当時は体調が完全には回復しておらず、私にはもともとアレルギーもあって先行きの不安が常につきまとっていました。
でも、12年前、初めて萩大島の人たちの暮らしに触れた時、「私の不安なんてちっぽけだ」と感じました。島にはコンビニどころか交番や信号機もないけれど、味噌も野菜も手づくり完全無農薬。また、当時、「萩大島船団丸」の漁師たちは漁に出るための船や備品の購入などで漁協に借金をしている人がほとんどでした。それでも彼らはいつも笑っていて、食卓にはいつも新鮮なお刺身が山盛りにされていました。そんな姿を見て「この人たちと一緒にいたら、お金なんてなくても生きていける」と思ったとたん、体の底から力が湧いてきたんです。
誰かとつなげた手は絶対に離したくない
あの時から私は心のままに生きています。長岡たちと自家出荷に取り組んだのも、私は自分の体のことがあってもともと食の安全への関心が高く、萩大島の人たちがふだん口にしているもののおいしさ、質の良さに衝撃を受けたからです。私は医師でもないし、看護師でもなく、何の力も持っていないけれど、これをたくさんの人に届けられたら、自分のように健康に悩まされた人の役に立てる。それってすごいな、と思いました。幼いころから抱いていた「人は生きるために働くのか。働くために生きるのか」という問いの答えがはっきりとわかった瞬間でした。
だから、農林水産省の六次産業化支援プログラムに提出した事業計画も、仮に長岡たちが「わしらにはできん」と言ったら、自分ひとりでもやるつもりで書きました。また、前例のほとんどない事業ではありましたが、計画の内容は突飛なものではなく、一つひとつのステップを着実に踏んで実現してきました。2022年10月現在、船団丸事業は全国に拡がり、全国11カ所で展開していますが、これも長岡をはじめ萩大島の漁師たちがコンサルタントとして活躍してくれ、各地の船団丸と1カ所ずつ関係性を築いてきた結果です。
挑戦はすれど、ギャンブルはしない。そして、立てた計画は必ずやり遂げる。これが私の鉄則です。背景には、「働くために命を落とす人がいない世の中にしたい」という思いがあります。簡単に実現できることではないかもしれないけれど、少なくとも、私自身が誰かとつなげた手は絶対に離したくありません。仕事の失敗で海に飛び込んだり、首を吊ったりしなくていい。大きな企業に勤めたり、お金持ちにならなくたって人は幸せに生きられるんだ、ということを体現したいんです。
「あの人がいたからよかった」と思われる人生に
「GHIBLI」の財務面はまだまだ安定していませんが、「萩大島船団丸」の漁師たちのほとんどが漁業への借金をこの10年で返済することができました。私にとって心からうれしかったのは、「わしは船団丸をやってきてよかったと思うとる」という長岡の言葉です。ダメでもともと。行けるところまで、行ってみよう−−−−。これが漁師たちと私の合言葉でした。今もこの先もそれは変わりません。
私が今あるのは、長岡たちだけでなく、「GHIBLI」や「船団丸」に関わるすべてのスタッフ、応援してくださった外部の方々がいたからです。「GHIBLI」のスタッフは私と志を同じくする人であることを基準に採用していたら、結果的に女性が多く、シングルマザー率が高いです。初の正社員として入社してくれた藤井信子さんもそうで、私が仕事で家を空けなければいけない時に息子を預かってもらうなどプライベートでも助けてもらいました。

現在中学3年生の長男が保育園に通っていたころ。幼いころは「おうちにいる普通のママがいい」と泣かれることも多く、私もつらかったが、今は理解してくれている
実は最近、私たちにとってとても悲しいできごとがありました。「GHIBLI」の女性スタッフの赤ちゃんが生後100日ほどで亡くなったのです。夏実ちゃんという名の女の子でした。当然、その女性スタッフは悲しみにくれ、私たちは慰める言葉もありませんでした。ところが、職場復帰した彼女は慰められるどころか仕事と子育ての両立で忙しそうにしている同僚たちを気遣って「私にできることは遠慮なく言ってね」と声をかけ、みんなを励ましてくれています。なかなかできることではないと、頭が下がります。
彼女の姿は私たち全員の日々の生活や仕事への向き合い方を変えたように思います。口にこそしませんが、「夏実ちゃんに恥じない生き方をしたい」という思いが「GHIBLI」に生まれていることを感じます。「人生100年」と言われる時代ですが、人生で大事なのは「長さ」ではなく「体積」。夏実ちゃんの人生は100日だったけれど、私たちの心に足跡を残しました。私も夏実ちゃんのように、この世から去った時に「あの人がいてよかった」と誰かから思われる人生を生きていきたいです。
写真/畑谷友幸、取材・文/泉彩子
 「ファーストペンギン
「ファーストペンギン
シングルマザーと漁師たちが挑んだ
船団丸の奇跡」(講談社)(10月6日発売)
*ライフシフト・ジャパンは、数多くのライフシフターのインタビューを通じて紡ぎだした「ライフシフトの法則」をフレームワークとして、一人ひとりが「100年ライフ」をポジティブに捉え、自分らしさを生かし、ワクワク楽しく生きていくためのワークショップ「LIFE SHIFT JOURNEY」(ライフシフト・ジャーニー)を提供しています。詳細はこちらをご覧ください。