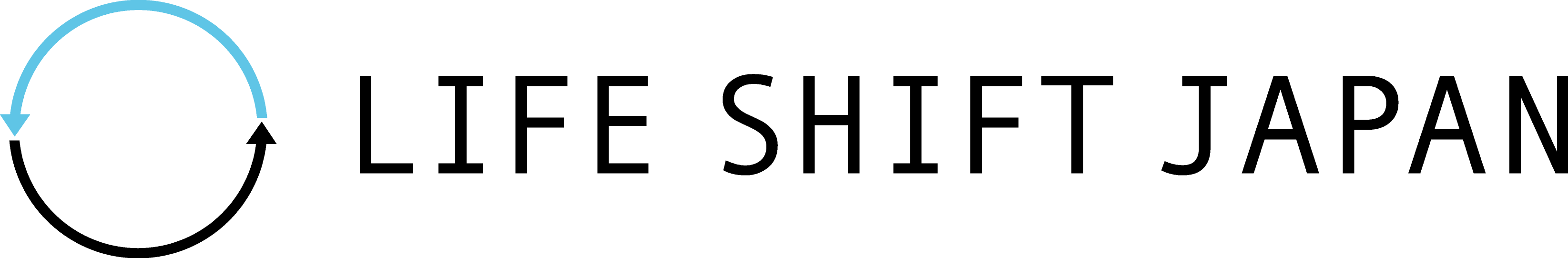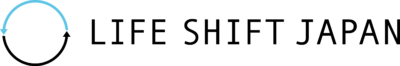秦 政(はた まこと)さん(No.91)/一般社団法人ひとつぶの種 代表
■1941年、三重県生まれ。1965年、慶應義塾大学商学部卒、日鐵商事株式会社入社。1969年、株式会社日本リクルートセンター(現リクルートホールディングス)入社、テスト部配属。営業経理部長を経て、1989年、障害者雇用促進特例子会社設立準備室を立ち上げ、準備室長就任。1990年、株式会社リクルートプラシス(現リクルートオフィスサポート)を設立し、専務取締役に就任。2001年退任後、日本障害者雇用促進協会・日本経団連障害者雇用アドバイザーを経て、2004年にNPO法人障がい者就業・雇用支援センターを立ち上げる。一方で、株式会社アドバンテッジリスクマネジメント顧問、厚生労働省の障がい者雇用に関する各種研究委員などを歴任。2012年3月、キューブ・インテグレーション株式会社を創業。2020年2月、一般社団法人ひとつぶの種を設立し代表理事に就任。
■家族:妻
■座右の銘: 「フェア」
「子どものころから、理不尽なことが大嫌いで、不公平が見過ごせない。『フェア』という言葉が好きなんです」と秦さん。
突然任された、障がい者雇用のための特例子会社の設立。やってみたら、「天職」だった
リクルートの営業経理部長をしていた47歳のある日、呼び出されて人事部に行くと、「障がい者雇用のための特例子会社の設立が経営会議で決まったので、立ち上げをお願いしたい」と人事部長に切り出されました。
話をするうちに、僕が呼ばれたのは、その半年ほど前に実施された、人事部による障がい者雇用に関するアンケートが理由だとわかりました。1989年当時、法定雇用率は1.6パーセントでしたが、リクルートにおける実質的な障がい者の雇用率はわずか0.1パーセント。改善策の検討を目的に、障がいのある人たちに委ねられる業務がどのくらいあるかを部署ごとに調査するアンケートでした。

創業メンバーに誘われ、27歳でリクルートに転職した。写真は営業経理部長時代。
実施時には意図を知らず、特別な資格や専門性がない人でもできる業務を洗い出し、「少なくとも5、6人分の業務がある」と回答しました。ほかの部署でも似たり寄ったりだと思っていたのですが、「ゼロ」と答えた部署がほとんどだったそうです。前向きな回答をした部門長がほかにいなかったことから、「秦に任せてみよう」ということになったのでしょう。
僕にとっては寝耳に水でしたが、特例子会社設立に向けて準備を始めると、「自分が本当にやりたかったのはこの仕事だ」と感じました。障がい者雇用をめぐる状況を知るにつけ、「社会を変えなければ」という気持ちが大きくなっていったからです。
変えたいと思ったのは、障がいのある人を「障がい者」としか見ない、社会一般のものの見方です。雇用という領域ひとつとっても、障がい者と健常者を最初から違えて制度が作られ、教育がなされ、受け入れ環境が整えられています。
しかし、障がいがある、なしの前に人は人です。人にはそれぞれ個性や能力や人生観の違いがあり、それは障がいのあるなしとは関係ないはずなのに、最初から「障がい者」というレッテルを持って全てが始まってしまう。この状況を何とかしたかったんです。
意味のないレッテルのためにチャンスすら与えられないというのは、おかしい
人にレッテルを貼ることが嫌いなのは根っからの性分です。生まれ育った環境も影響しているかもしれません。三重県の田舎で戦前に生まれ、被差別部落が身近にあって、そこには親しい友人たちもいました。自分よりはるかに優秀だった彼らがひどい偏見や差別に苦しみ、社会の目や経済的な事情ゆえに進学できない姿を見て、意味のないレッテルのためにチャンスすら与えられないということに対し、おかしいと強く感じ、社会に出てからもその思いを持ち続けていました。
だから、障がい者雇用促進のための特例子会社・リクルートプラシス(現リクルートオフィスサポート)を立ち上げるにあたっては、「障がいのある、なしにかかわらず、社員にはマックスのチャンスを提供するぞ」と固く心に決め、退路を断ちました。人事部からは「出向」の選択肢も与えられましたが、一般的に出向した社員は数年で本社に戻ります。それでは腰を据えて取り組めないと考え、リクルートとの雇用契約を終了する「転籍」の道を選んだんです。
特例子会社というのは「障害者雇用促進法」で定められた、障がい者の雇用に配慮あるいは特化した会社のことで、設立時の「プラシス」は社員34人中15人が障がいのある人たちでした。一人ひとりを戦力にしないと、会社の将来はありません。初めて、経営というのはこういうものなんだと知りました。必死で取り組み、障がいのある彼ら、彼女らもそれに応えてくれました。チャンスを与えられ、体験を積めば、障がいがあっても、活躍できる人はたくさんいる。彼ら、彼女らのおかげで、自分の考えは間違っていないと実感できました。
58歳で「プラシス」を退職。自分のやりたいことをフリーハンドで描いてみたかった
「プラシス」の専務取締役は58歳まで11年間務めました。それ以前から、会社には「50代のうちに次の道に進みたい」と話をしていました。障がい者雇用をめぐる状況について知るにつれ、もっと勉強したいという思いが強まり、体力も気力もある50代のうちに、と考えたからです。
「プラシス」が軌道に乗っていなければ、自分自身の将来を考える余裕はなかったでしょう。しかし、設立5年が過ぎたころには組織の地固めができ、経営を任える人材も育ってくれていました。一方、僕自身はそのころから社外での活動が増えていきました。自分自身の経験をほかの企業と共有することで、障がい者雇用に対する企業の意識を変えていければという思いから、東京労働局に働きかけて企業向けのセミナーの講師をやらせてもらったのがはじまりです。最初は数件でしたが、都内全域のハローワークや全国の障がい者支援団体からお声がかかるようになりました。
会社の外の世界を見ることによって感じたのは、社会にはまだまだ変えるべきことがあるということ。「プラシス」は成長し、僕がいなくても十分歩んでいけるけれど、社会には自分の力を必要としている場所がある。勝手にそう思い込み、「プラシス」を退く決意をしました。会社にいながら社外の活動を続けることもできたかもしれませんが、一度組織を離れ、自分のやりたいことをフリーハンドで描いてみたかったんです。
すぐには周囲に理解されなくても、自分の思いを大事にし、思ったことを発信し続けた
「プラシス」を辞めてしばらくはゆっくりしようと思っていたのですが、仕事でおつき合いのあった経団連事務局から声をかけていただき、退職翌月から厚生労働省の外郭団体で非常勤のアドバイザーを始めました。全国にネットワークがある組織なので、地域ごとの課題を学ぶ絶好の機会だと考えたんです。
ところが、実際に仕事をしてみると、物事の進め方があまりにも「お役所的」で、せっかくの地域の生の声が行政に届けられていませんでした。そこで、改善のためにさまざまな提案をしたものの、状況は変わらず、業を煮やして4年目の契約更新直後に辞めました。
団体の幹部にはよく「それは秦説ですね」と言われました。突飛なことを言っていたみたいですね(笑)。ただ、職員の皆さんには理解してもらっていたように思います。僕が辞めると聞いて、非常勤では異例の送別会まで開いてくれ、ありがたかったです。
団体を退職後は、障がい者の就業・雇用を支援するためのNPO法人障がい者就業・雇用支援センターを立ち上げ、ここでは新たなテーマとして、障がい者の在宅就業の促進に取り組みました。「プラシス」時代から、通勤が障がい者の就労の大きなハードルになっていることが気になっていたからです。
コロナ禍の影響もあり、今でこそ在宅で働くことが社会で注目されていますが、2000年代半ばのこと。企業に働きかけると、総論では賛同してくれるのですが、在宅就業に対するイメージがないために不安が生まれ、各論となると話が前に進みませんでした。
また、国による障がい者の在宅就業支援も当時はごく限られた職種に限定されており、在宅での就労環境にも細かな制約が設けられていて、より多くの人が支援を受けられるよう厚生労働省に提言をして、ケンカに(笑)。すべてが早すぎたんですね。
でも、自分の思いを大事にし、思ったことを発信し続けていたことにより、多くの仲間と出会えました。また、5、6年前には厚生労働省から「障がい者の在宅就業に長くかかわっている立場から話を聞かせてほしい」と連絡があり、ちょうどそのころから、在宅就業の障がい者を雇用する企業への助成金の支給基準が緩和されるなど障がい者の在宅就業をめぐる状況が前進しはじめました。最近のリモートワークの普及も追い風になるでしょう。巳年生まれは「しぶとさ」が特徴と言いますが、巳年で良かったです(笑)
60代から取り組んだライフテーマのひとつが、精神障がい者の支援だった
「障がい者の在宅就業促進」というテーマの一方で、もうひとつ力を入れて取り組み始めたのが「精神障がい者の雇用」です。2004年に「障がい者就業・雇用支援センター」を立ち上げたのと同時に、「アドバンテッジリスクマネジメント」の顧問として精神疾患者の職務復帰サポートプロクラムや転職サポート事業に携わり、2012年には仲間と企業のメンタルヘルスケア支援をする会社を作りました。
「精神障がい者の雇用」も「プラシス」時代から気になっていたテーマです。当時から精神障がい者は増えており、うつ病などの精神疾患を持つ社員にどう向き合えばいいのかと悩む企業は少なくありませんでした。また、法定雇用率は時代とともに引き上げられ、身体障がい者や知的障がい者だけでなく、精神障がい者の活躍の場を広げていかなければ、雇用率を改善できません。多くの企業が精神障がい者の雇用に課題意識を感じていました。
一方で、精神障がい者は身体障がい者や知的障がい者に比べて障がいが目に見えにくく、個別性も高いことから、支援環境の整備をしづらいところがあります。わからないこと、知らないことが多いために雇用が進まず、もともとは「プラシス」にも精神障がい者は在籍していませんでした。そこで、まずは自分が精神障がいを持つ人たちについて知りたいとある就労支援センターに数日間弟子入りし、彼ら、彼女らのことをイチから教わりました。
その後もそこに足繁く通い、精神障がいを持つ人たちの思いや体調変化を見ていくうちにわかったのは、チャンスを提供し、長い目で見守ってくれる環境さえあれば、彼ら、彼女らはすごく力を発揮できる人たちだということ。そして、そのことを社会が知らないことによって、雇用が進まないのだとしたら、知らせることで、状況を変えていかなければと思ったんです。
夫婦で沖縄で暮らそうと家を建てはじめた矢先、妻が他界。悲しみに暮れた
47歳で障がい者の支援という「天職」に出合ったのは年齢的に早くはないかもしれませんが、20年続けたころから少しずついろいろな思いが形になってきました。でも、障がい者に対する世の中の見方は簡単には変化せず、70歳を過ぎても、「リタイア」という言葉を思い浮かべることはありませんでした。一方、プライベートでは2015年に金婚式を迎え、そのころから、沖縄にセカウンドハウスを持ち、妻と暮らそうと計画しはじめました。
沖縄には講演活動などで20年にわたって何度も訪れていました。暮らすことを決めた理由のひとつは、美しい自然。沖縄の住まいが、都会の中で精神的な苦しさを感じている人たちのリトリートの場になれば、と考えたんです。
これは僕自身がリクルート時代に岩手県・安比高原で研修を受け、自然の中でリラックスし、自分と向き合うことがどれだけ心と体にいいかを肌で感じたことが原点。精神疾患のある人たちの支援においても、厚生労働省と連携して静岡の農場でのメンタルへルス研修を10回実施したりして、自然の中で過ごすことがメンタルヘルスに与える効果を確信していました。
もうひとつの理由は沖縄の美しい光景の陰にある、貧困の現実です。仕事が少なくて失業率が高いことから、離婚率も高く、教育にも影響を与えて、仕事に就きにくいという負のスパイラルが起きています。この現実を見てほしいという思いを以前から持っていて、沖縄の僕の家に友人・知人に遊びに来てもらい、観光だけではわからない現実を感じとってくれれば、という願いもありました。
沖縄本島北部美ら海水族館からほど近い、瀬底島に土地を見つけ、家を建てはじめたのは2017年2月。その翌月、妻に病気が見つかりました。すべての仕事を投げ打って看病しましたが、病気の進行が早く、病気発覚からわずか4カ月後に妻はこの世を去りました。悲しみに暮れ、夫婦の思い出がいっぱいの東京にいることさえつらくて、2018年3月、家の完成と同時に逃げるように沖縄に移り住みました。76歳のときです。
ひとり移り住んだ沖縄での予想外の日々の中、人生の新たなパートナーとの出会いがあった
沖縄に移り住んだ当初は、自分の人生は終わった、と気力をなくし、仕事もやめて隠居するつもりでした。ところが、僕を心配した友人や知人、仕事仲間やずっと顧問をしてきた社会人アメリカンフットボールチームの面々、元部下たちが次々と沖縄に来てくれて、気づけば、多い年は70組を迎える事態に。ありがたいやら、何やら、想像もしていなかった日々でした(笑)。

沖縄を訪ねてきてくれた仲間と。

島内外の友人たちを招いたクリスマスパーティーの様子。60人が集った。
沖縄の家を訪ねてくれた人たちの中に、現在の妻もいました。当時京都市役所の職員で、ずいぶん前に京都市の障がい者雇用に関する外部委員の仕事をしていたころの知り合いでした。2019年6月に京都から友人と来てくれて、3日間語り合った時に、「あ、自分はこの人と一緒にいたいんだ」と感じ、2019年11月に京都を訪ねて気持ちを伝えました。
彼女は障がいのある人たちの支援に長年携わっていて、描いている夢が僕と同じでした。障がい者と健常者の垣根をなくしたい、という夢です。そして、精神疾患や障がいなどさまざまな理由で行政の就労支援を受けることが難しく、置いてきぼりにされている人たちに何かをしたい、という思いも一致していました。
夫婦で京都に一般社団法人を設立。生きづらさを抱えた人たちがほっとできる場所を目指す
ふたりの思いを形にしようと、2020年2月に私が京都に住まいを移し、京都市北区に一般社団法人ひとつぶの種を立ち上げました。「ひとつぶの種」が目指すのは、引きこもり状態にあったり、精神疾患に悩むなど生きづらさを抱えている人たちが自分の強みや魅力を発見し、自分らしく前を向いていただくための支援を行うことです。

「ひとつぶの種」の内観。「いい雰囲気でしょう。ぜひ遊びに来てください」
活動を始めた矢先、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、準備に少し時間がかかりましたが、2020年11月に物件の工事が完了。2021年4月の本格始動に向け、現在は絵手紙教室や喫茶の提供、寄贈書で作った「ひと箱古本屋」、手づくり品などを展示販売できる「レンタルボックス」などの活動を試験的にやっているところです。中でも絵手紙教室はとても好評で、評判が伝わり、対象としている大人のほかに、近所の放課後等デイサービスに通う生徒さんも来てくれています。
何度も通ってくれる子がいるんですよ。何をするわけでもないけれど、ゆったりとでき、人とおしゃべりできて、自分に負い目を感じないで好きなピアノが弾けて。これでいいんだろう、と思うんですよ。仕事に就くためのスキルを身につけたり、知識を学ぶ。もちろん、それも大事なことだけど、その前にもっと、日常の中で自分はこれでいいんだという安心感を持ってほしいと思うんですよね。
100まで生きることを決めたので、健康管理は絶対
僕の人生って、ひとことで言えば、「人が好き」。それに尽きるんですよ。仕事の覚えは悪いけれど、会った人のことは覚えています。「ひとつぶの種」にもたくさんの友人・知人が「遊びに行きたい」と言ってくれていて、僕は幸せ者ですよね。

35年間顧問を務めている社会人アメリカンフットボールチーム「オービックシーガルズ」の試合にて。さまざまな交友関係を大事にしてきた。
なんだかんだ忙しく仕事をしてきて、家族と過ごす時間が多かったとは言えず、亡くなった妻がどう感じていたかは、今となってはわかりません。ただ、3人の娘が優しい子に育ってくれていることがすべてを表している気がして、亡き妻に感謝するばかりです。
娘のひとりが大きくなってきたころに、ふと言った言葉が印象的なんですよ。「お父さんは本当に忙しくて、朝早く出て行って、夜いつ帰るのかもわからないけど、たまに仕事の話をすると、『今日、こんな人と会ったんだよ』と本当に楽しそうにしゃべってる」と。
娘たちはそれぞれ自分で選んだ道をしっかりと歩んでいて、再婚の話も応援してくれました。妻にも成人した息子がおり、ふた周り年上の私との再婚に彼がどう反応するか彼女は心配だったようですが、彼は「20歳と40歳じゃ歳が違いすぎるけど、50歳と70歳じゃ変わらへんやん」と言ってくれたそうです。息子夫婦は映像関連の仕事をしていて、「ひとつぶの種」のホームページも作ってくれました。
実は、妻は「結婚はしなくてもいいのでは?」と言っていたのですが、私としては責任を果たしたいという思いがあり、2020年11月に入籍してもらいました。財産の半分は元妻のものなので3人の娘に残し、後の半分は妻も含めて4人にと決めて遺言書を書いています。
沖縄の家は、今後、「ひとつぶの種」で出会った人たちのリトリートの場所として生かせたら、と思っています。沖縄では、98歳の時に「カジマヤー」という長寿のお祝いをするんですよ。「カジマヤー」まで20年。それまでには「ひとつぶの種」がなんとかひとり歩きするようになり、ここから一人ひとりが巣立っていく状態になるよう頑張るつもりです。100まで生きることを決めたので、健康管理は絶対。最近、スポーツクラブにも通い始めました。

ジムは週2回。トレーナー指導のもと体幹を鍛え、水中を歩く。そして朝ご飯をしっかり食べ、よく眠り、よくおしゃべりをする。
自分たちで名づけておいてナンですが、「種」っていいなと思うんですよ。「種」って見ただけでは、何が育つかわからないじゃないですか。そこから芽が出て、「あ、これはこんな木だったんだ」、「こんな実がなるんだ」と成長していくごとに発見がある。種っていうのはね、始まりなんですよ。「ひとつぶの種」、いい名前でしょ(笑)。「ひとつぶの種」は、僕たちの子ども。夫婦で種を育てていきます。

(取材・文/泉 彩子)