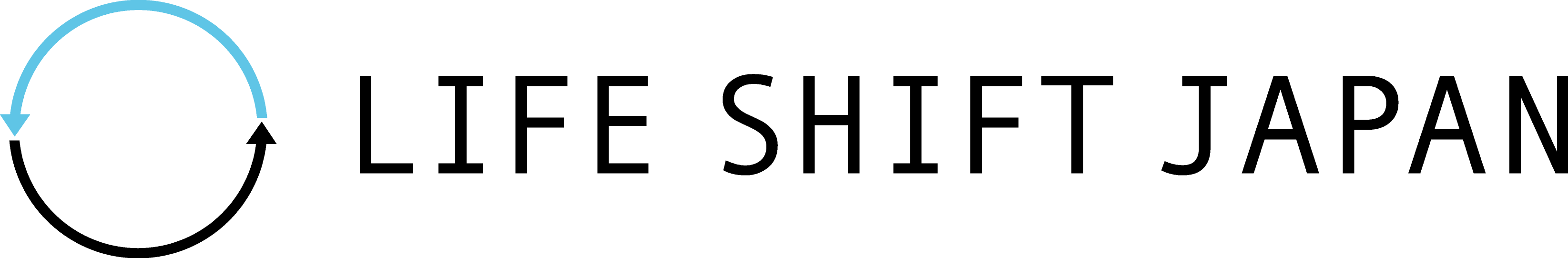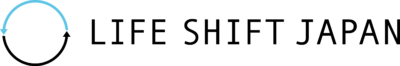33年間勤務した富士フイルムを56歳で退職し、2カ月後に“ひとり写真店”「吉村寫眞商店」を設立した吉村英紀さん。インスタントカメラ「チェキ」の再生プロジェクトで活躍するなど充実した会社生活を送っていた吉村さんが定年の60歳を待たず独立したのはなぜだったのでしょうか。
吉村英紀さん(No.106/合同会社吉村寫眞商店 代表)
■1964年愛媛県生まれ。1988年早稲田大学政治経済学部卒業後、富士写真フイルム株式会社(現・富士フイルム株式会社)入社。感熱紙の営業を経て、2000年写真関連部門に異動。以降、デジカメプリント店頭受付機、フィルム、レンズ付きフィルム「写ルンです」、インスタントカメラ「チェキ」、プリント関連サービスなどの国内マーケティングを手がける。東日本大震災直後には、富士フイルム写真救済プロジェクトのサブリーダーを務めた。2014年富士フイルム初の直営写真店「ワンダーフォトショップ」立ち上げに参画。以降、2021年10月まで運営に携わる。2021年10月に富士フイルムイメージングシステムズ株式会社を退職。2021年12月2日、合同会社吉村寫眞商店を起業。一般社団法人写真整理協会理事。2023年4月より相模女子大学大学院社会起業研究科在学。
■家族:妻、長女、長男
■座右の銘:「迷ったら積極的な方を取る」
「行こうか行くまいか」くらいのちょっとした迷いがある時は、積極的な方を選択するようにしている。「結局、行くと新しい出会いや発見があったりしてプラスになることがほとんどなので」と吉村さん。
「人を幸せにするモノ」に携わりたいと富士フイルムに入社
富士フイルムに入社したのは、同好会的な和気あいあいとした雰囲気があり、人を大切にする会社だと感じたことが大きかったように思います。大学時代に合気道の同好会に所属していたこともあって、体育会的な組織よりも同好会的な組織がいいなあと思って。当時富士フイルムのCMに出演していた南野陽子さんのファンだったことも影響していたかもしれません(笑)。
当時は金融や商社が人気でしたが、お金やよくわからないモノのことをやるよりは「人を幸せにする写真がいい」と思いました。同年代で富士フイルムに入社した人は多かれ少なかれ同じような思いを持っていたんじゃないかと思います。
入社後12年間は産業材料の感熱紙を扱う部署で働きました。写真のトップメーカーに入社したと思っていたら、「よく知らない紙」を扱うマイナーな部署に配属されて最初は面食らいました。でも、やってみたら、すごく楽しかったんですよ。当時の富士フイルムは感熱紙メーカーとしては業界4位。市場での劣勢を巻き返すには競合他社と同じことをしているわけにはいきませんから、新しいアイデアをあれやこれやと考えるのが面白かったし、少人数の部署だったので連帯感もありました。

入社2、3年目のころ、部署の懇親会で。感熱紙を担当した12年間はものづくりの会社で働くこと、愛着を持って製品を育てることの醍醐味を存分に味わうことができました。
産業材料部門を経て、35歳で「写真ビジネスの総本山」に異動
感熱紙の部署を離れ、「感材部」というフィルムやプリントを扱う部署に異動したのは2000年。35歳の時でした。感材部は写真ビジネスの総本山、富士フイルムの中枢の中の中枢です。辺境で伸び伸びやっていたらいきなり大変なところに異動になった、と身が引き締まりました。
最初に担当したのはデジカメプリントの店頭受付機。今では当たり前に写真店にあるものですが、まだ世の中にはありませんでした。2年後、今度はカラーネガフィルムの担当に。会社のメイン商品でしたが、私が担当になるやいなや、ジェットコースターのロックが外れたようにフィルムの需要が急落し始めました。
デジタル化の波は急激でした。感材部に来た時は社内の雰囲気も「フィルムは無くならない」という感じだったのが、その頃には「アナログは時代遅れ、デジタルが当たり前」という雰囲気に変わっていっていました。
私もデジタル化の流れを「止めようのないもの」とは思ってました。でも、当時、私は「新参者」として勉強したいという思いもあって、デジカメとフィルムの両方のカメラを使ってたくさんの写真を撮っていたんですね。撮影してはプリントし、両者を見比べたりしていていたので、「フィルムならではの良さ」があると実感していました。それに、何より担当したフィルムというプロダクトをすっかり好きになっていました。
社外との連携プロジェクトで得た新たな視点
フィルム担当になって2年目のこと。フィルムの新しい可能性を生み出すことを目的とした部門横断プロジェクト(FKプロジェクト。FKは「フィルム強化」の頭文字)が立ち上がり、担当だった私もアサインされて1年ほど専任で携わることになります。
このプロジェクトではコンサルタントやクリエイターなど社外の方たちとも一緒に仕事をし、彼らの自分たちとは異なる視点から、さまざまなことを学びました。
例えば、「フィルムの価値は“機能”だけじゃない」ということ。社内で「フィルムが生き残るにはどうすればいいか」というような話をする時に、私たちは「高感度」「優れた粒状性」といった「機能」を価値基準にしていて、そういうものだと思っていたんですね。でも、彼らは、フィルムの価値を「機能」よりも、それによって表現される風合いやテイストといった情緒的な要素に重きを置いて評価していました。
フィルムに「情緒的価値」というこれまで注目していなかった価値がある、という気づきは私たちにとってフィルムビジネスの新たな展望を感じさせるものでした。だから、チームには「未知の領域だけど、まずはやってみよう」という活気がありましたね。社外の方たちにアドバイスをもらいながら、情緒的価値を高めるフィルムやカメラ、プリントの焼き方、さらにはそれを提供する実験店舗(名称は「富士寫眞店本店工房」を予定していた)について研究所、生産、営業の各部門から集ったメンバーたちと休日返上で企画を練り上げていきました。
結局、FKプロジェクトは富士フイルムが「構造改革」という名の大リストラを行う直前に解散することになりましたが、この時の「会社の外に出て現場の人たちに話を聞く」「多様な社外の人たちと協業する」「今までとは異なる切り口で価値を考えてみる」という経験は、その後私が仕事をしていく上で大きな資産になりました。

FKプロジェクト時代。隣にいるのは、一緒に仕事をしていたクリエイターさん。
「半歩出る」を心がけ、気になる人を訪ねては話を聞いた
プロジェクト解散後は、ケータイプリンタ等のマーケティングを経て再びフィルムを中心としたアナログ商品をまとめて担当することになりました。2000年代半ばのことです。このころ私は会社の外に出て、気になる人に会いに行っては写真について話を聞いていました。
すると、私が担当するアナログ商品について世間一般も社内も完全に諦めムードなのに、デジタルよりもアナログの方が「好き」とか「楽しい」と話す人たちを見つけたんです。それが後に「カメラ女子」と呼ばれるようになる、当時20代半ばから後半の女性たち。それまで写真業界がメインターゲットにはしていなかった顧客層でした。
会社の外に出て見つけた、こうしたたくさんの気づきが実を結んだのが、40代半ば、2000年代後半に携わったフィルムカメラ「ナチュラ」やインスタントカメラ「チェキ」の取り組みです。「チェキ」は1998年に発売されて年間100万台を販売するヒット商品になったものの、2005年にはピークの10分の1に落ち込んでいましたが、この取り組みでデジタル全盛期にも関わらずチェキは復活。以降販売台数を伸ばし続けています。
「チェキ」の数字が伸びたのは、もちろんうれしかったです。でも、私にとって大きかったのは、フィルムで写真を撮るのが好きだったり、プリントした写真を身近な人たちとのコミニュケーションツールとして楽しんでいたりする人たちにたくさん出会い、写真が持つ「“もの”としての価値」を確かめられたことです。「写真」にはビジネスとしての可能性がまだまだある、と希望を感じましたし、FKプロジェクトでやろうとしていたことは間違いじゃなかったと思いました。

2009年頃、チェキグループのメンバーと。デジタル全盛でアゲインストな環境でしたが、自由に動けて手ごたえも実感でき、充実した日々でした。
アナログ商品全般を担当後、次に携わったのはフォトブックをはじめとしたプリント関連サービス全般のマーケティングでした。スマホの登場でカタチにしなくても写真を見たり残したり楽しんだり出来る時代になり、「写真をカタチにすることの価値って何なのだろう」、「どういうカタチにしたらユーザーは喜んでくれるのだろう」、そんなことをずっと考えていました。
転機は2011年4月。東日本大震災が起きた1カ月後、津波の被害で泥まみれになった写真を洗って再生する「写真救済プロジェクト」のメンバーとして、被災地に入った時のこと。避難所のリーダーから「写真やアルバムが今まで生きてきた証となり、これから生きていく支えになる」という言葉を聞きました。
また、ボランティアの人たちが一生懸命に津波で汚れた写真をキレイにして持ち主に返そうと格闘している姿を見て、自分たちが思っている以上に写真は大切に思われているということ、そして、写真はカタチにしてこそ価値があるのだということを改めて感じました。それ以来、「写真をカタチにすること」にこだわり続けて仕事をすることになります。

2011年5月、名取市の閖上小学校の体育館にて(吉村撮影)。富士フイルム写真救済プロジェクトの活動で大量の写真やアルバムに向き合って作業したことが、現在の仕事にも生きています。
50歳を前に、会社と自分の方向性にズレを感じはじめた
入社以来、紆余曲折はありましたが、会社を辞めようと考えたことはなかったんです。ものづくりの会社で働くことや、組織で仕事をするのが自分に合っていると思っていたし、「写真」の仕事が好きだったからです。会社を辞めてまでやりたいこともありませんでした。
ただ、50を過ぎたあたりから、会社が「写真の仕事」で目指す方向性と、自分がやりたいことにズレを感じはじめていました。マスではない、もっとニッチなところに新たな写真のニーズを感じていたし、そういう現場に近いところで手触り感のある写真の価値を生み出していきたいという思いが強くなっていたんです。
富士フイルムの直営写真店「ワンダーフォトショップ」の運営に関わっていたことも影響しているかもしれません。お店の現場でいろいろな企画を考え、自分で実際に手足を動かして企画を実現して、それにお客さんが反応してくれてお金を払ってくれる。リアルにそれらを体感して純粋に「面白い」と思ったし、大変だったけどワクワクしたし、お客さんに喜んでもらえたり感謝されたりするのがうれしかった。社内のオフィスで仕事をしているよりも、現場で手足を動かして仕事をする方がずっとビジネスのダイナミズムを感じました。

直営写真店「ワンダーフォトショップ」のスタッフと。店も私にとっては商品と同じで、我が子のように思いながら仕事をしていました。
ふと気づけば、幻に終わったFKプロジェクトの実験店舗「富士寫眞店本店工房」で私たちがやりたかったことがそこに詰まっていました。もっとさかのぼると、そこには入社の時に思い描いていた「写真は人を幸せにする」がリアルにありました。
一方で、リアルなお店を運営してわかったことがあります。それは、店舗という箱があってお客さんに来てもらってプリントの生産をやっていると、外に出て営業する余裕が生まれにくいということです。これからの写真ビジネスはお店でお客さんを待っているのではなく、お客さんに提案しにいく「攻めの営業」が必須だと私は考えていましたが、箱と設備を抱えているとそれがなかなかできません。
プリント商材を生産するお店や工場は全国各地にあるし、そこで作られている商材のことは自分が今まで携わってきたからよくわかっている。だから必要なのにできていない「お客さんへの提案営業」を自分がやることで、写真の新しい需要が生み出せるんじゃないか——-。そんな考えから、店舗や設備を持たずに企画と提案営業で写真需要を創る「ひとり写真店」という発想がひらめきました。
会社でやりたいことはだいたいやれたし、これからやりたいことはマスというよりはニッチな市場での提案営業かも。そんな思いが膨らんできた時に早期退職の募集があり、「今が潮時なのかもしれない」と考えて会社を辞めることにしました。
誰もがいずれ「大きな船」を降りなければならない
富士フイルムを退職したのは、56歳最後の日。定年まであと3年でしたし、やりたい仕事もやれていましたから、早期退職の募集のようなきっかけがなかったら60歳までは会社に残っていたかもしれません。
亡くなった父が退職後も80代まで働いていたのを見ていたこともあって、私も「80歳まで働きたい」と思っていました。誰もがいずれはこの会社という「大きな船」を降りなければなりません。定年後、再雇用で会社に残るという選択肢もありますが、富士フイルムの場合、最長でも65歳までです。体力、気力、経験、人脈がある50代のうちに「小舟」で漕ぎ出した方が80歳まで働けるのではと考え、早期退職への応募を決めました。
退職から2カ月後、2021年12月に「吉村寫眞商店」を設立しました。オフィスは自宅で、社長一人・従業員ゼロの合同会社です。会社員時代は「富士フイルムの吉村さん」でしたが、独立するとなれば、自分の名前でやっていかなければなりません。皆さんに覚えてもらいやすいように、そして、独立への覚悟も込めて社名を決めました。「写真」の文字は「富士寫眞店本店工房」と同じ旧字に。先日、FKプロジェクトでご一緒したクリエイターの方に名刺を渡したらニヤっとされました(笑)。
「吉村寫眞商店」の事業の柱はふたつ。ひとつはBtoBの「コンテンツ事業」で、富士フイルム時代に直営店運営の一環で数多くの写真展を企画したり、プリントサービスの需要創造に携わってきた経験を生かし、アイドルの写真展やグッズの企画・提案を行っています。
もうひとつがBtoCの「写真整理事業」。家庭に眠っている写真のデジタル化をお手伝いし、ご要望によってはフォトブックや額装など日常的に気軽に見返せるプロダクトへのリメイクもサポートしています。

お客さまから預かった写真は、バラ写真、ポケットアルバム、貼るタイプのアルバムなどの形態にかかわらず写真1枚ずつをスキャンしています。
会社員なら毎月決まったお給料を口座に振り込んでもらえるけれど、独立後はそうはいきません。正直、1年目は「稼ぐって難しいな」と思いましたし、会社ってすごいなって改めて思いました。今も大変さは変わりませんが、運良く仕事はいただけていて、収入は個人年金も併せて企業の中堅社員くらいです。
商品やイベントの企画を考えて提案する、自分で汗をかいてそれを実行する、お客さんに喜んでもらってお金をいただく——-。在職中に意識してやっていたことが独立後もそのまま生きているのを感じます。
仕事の話をくださったり、助け舟を出してくれたりするのはかつて仕事をご一緒したことがあるなど何かしらご縁のあった社外の人たちで本当にありがたく感じます。一方で、「吉村さんにはあの時に助けてもらったから」と言ってもらったりして、頑張って仕事をしていた過去の自分にも感謝しています。
富士フイルム退職について妻は、強く反対はしないものの賛成もしないという感じで、内心どう思っていたかはわかりません。心配もかけたかもしれませんが、専業主婦だった妻も今は少しずつ仕事を始めていて、それも良かったのかもしれないなと思っています。
現在、「コンテンツ事業」と「写真整理事業」の売上比は9対1。多くの方が処理に困って押し入れや物置にしまい込んでいる写真やアルバムを放っておきたくないという思いがあって、本当はこの比率を半々くらいにはしたいんです。このままでは富士フイルムで私たちが「価値がある」と思ってきて作ってきたものが、厄介ものとして捨てられる「負の資産」になってしまいますから…。
ただ、「写真整理事業」はお客さまからの反応に手ごたえを得てはいるものの、サービス内容やビジネスの仕組みに課題を感じています。自分の会社で小さく事業を継続していくことはできたとしても、それだけでは全国のさまざまな家庭で「負の資産」になりつつある写真やアルバムを「正の資産」にするという大きな課題は解決できないからです。
そこで、2022年10月から一般社団法人写真整理協会の理事も務め、同じ思いを持つ方たちと一緒に活動しています。また、課題解決のための考え方や手法などを学びながら、地域の人たちともつながりつつビジネスモデルをブラッシュアップしていきたいと考え、2023年4月から地元の大学院の社会起業研究科に通っています。将来的には、写真整理協会や写真整理アドバイザー、富士フイルム、関連企業ともアライアンスを組みながら、社会全体に活動を広げられたらうれしいですね。
人生100年と考えたら、50代後半でも社会に出てからの折り返し地点をちょっと過ぎたあたり。だから、会社人生の起承転結が終わって次の「起」が始まった気分でいます。私たちの世代はまだまだ元気だし、世の中を面白くしていける。同世代の方たちと語り合いたいし、応援もしたいという気持ちから「ライフシフト・ジャパン」のライフシフト パートナーも務めています。皆さんと一緒に、人生100年時代をわくわく楽しく生きていける社会をつくって行けたら、と思っています。
(取材・文/泉彩子)
*ライフシフト・ジャパンは、数多くのライフシフターのインタビューを通じて紡ぎだした「ライフシフトの法則」をフレームワークとして、一人ひとりが「100年ライフ」をポジティブに捉え、自分らしさを生かし、ワクワク楽しく生きていくためのワークショップ「LIFE SHIFT JOURNEY」(ライフシフト・ジャーニー)を提供しています。詳細はこちらをご覧ください。